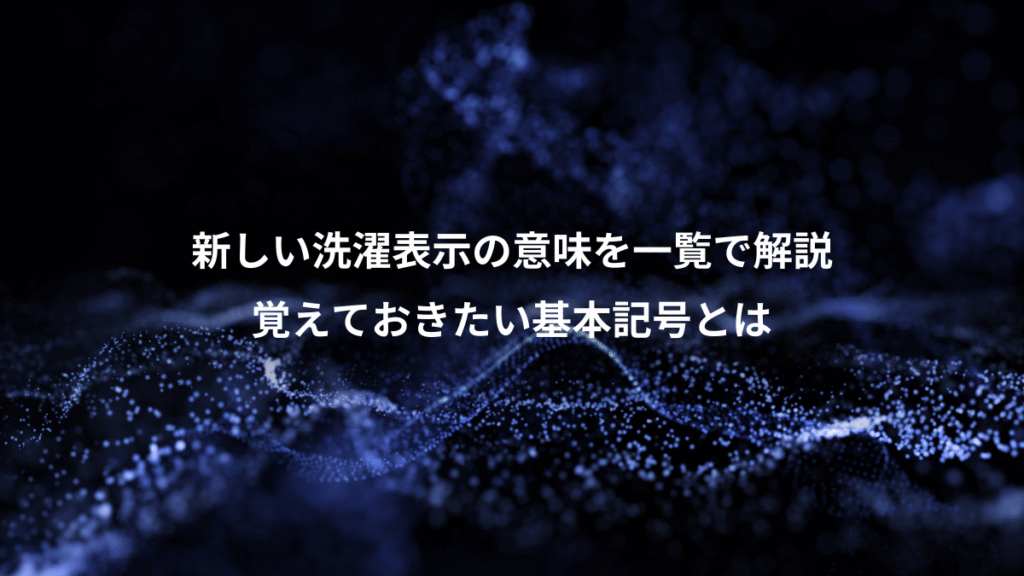お気に入りのセーターが縮んでしまったり、白いシャツに色が移ってしまったり、洗濯での失敗は誰にでも経験があるのではないでしょうか。こうした失敗の多くは、衣類に付けられた「洗濯表示」を正しく理解していれば防げるかもしれません。洗濯表示は、その衣類を長く大切に着るための、メーカーからの「取扱説明書」ともいえる重要な情報です。
2016年12月、この洗濯表示が国際規格に合わせた新しいデザインに一新されました。記号の種類が増え、より詳細な情報が伝わるようになった一方で、「なんだか複雑でよくわからない」と感じている方も少なくないでしょう。
この記事では、新しい洗濯表示の基本的な見方から、全41種類の記号の意味まで、初心者にも分かりやすく一覧で徹底解説します。旧表示との違いや、多くの人が抱く疑問にも丁寧にお答えします。この記事を読めば、もう洗濯表示の前で迷うことはありません。正しい知識を身につけ、あなたの大切な衣類をいつまでも美しい状態で保ちましょう。
目次
洗濯表示とは?
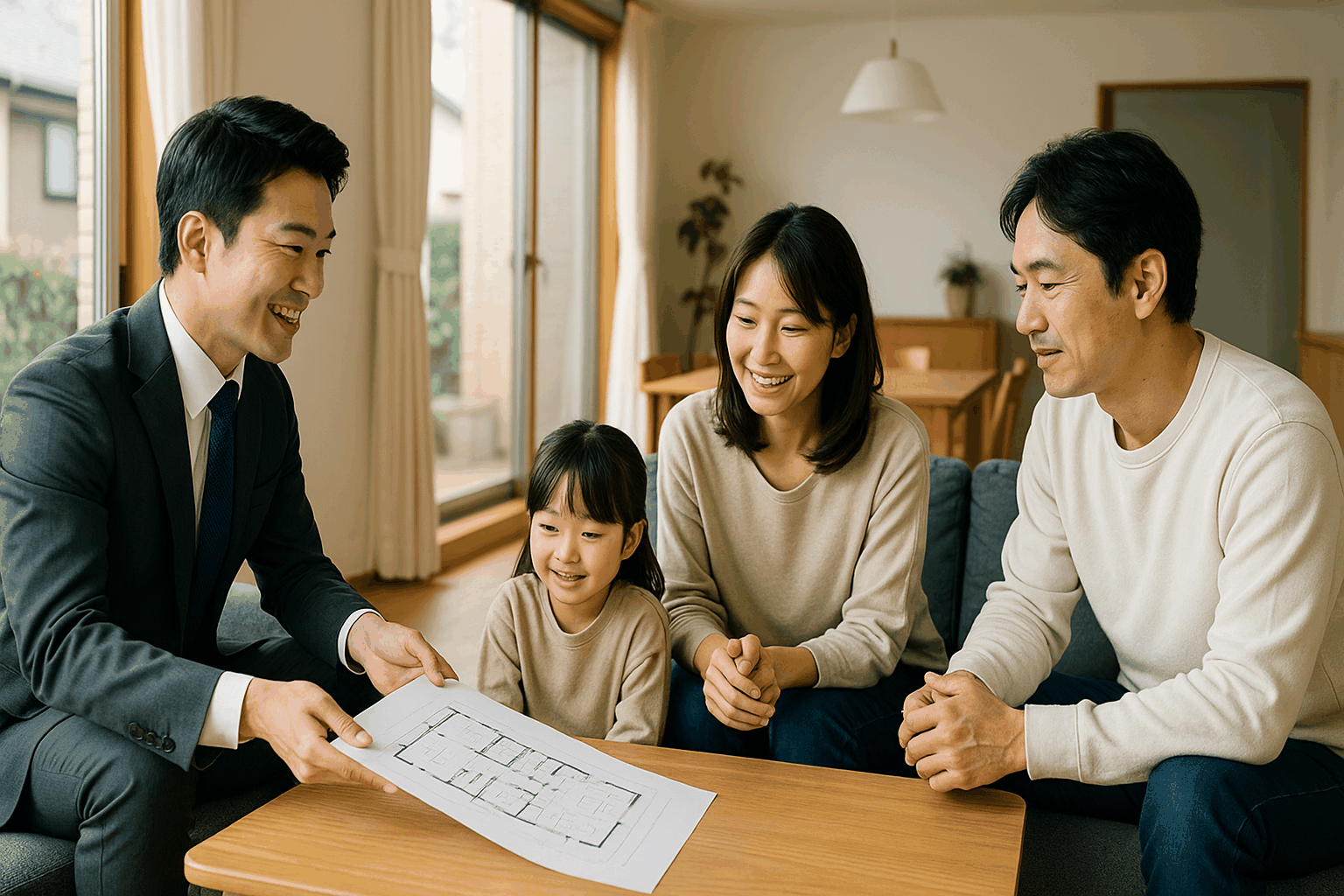
洗濯表示とは、衣類などの繊維製品に付けられた、洗濯や手入れの方法を指示する記号(ピクトグラム)のことです。これは、消費者が製品の品質を損なうことなく、適切に取り扱うために、製造者や販売者が提供する義務がある情報です。具体的には、「繊維製品品質表示規程」という法律に基づいて定められたJIS規格(JIS L 0001)によって、表示する内容や方法が細かく決められています。
普段何気なく見ているこのタグには、衣類を長持ちさせるためのヒントが凝縮されています。例えば、Tシャツとウールのセーターでは、素材の特性が全く異なります。Tシャツは丈夫で家庭の洗濯機で気軽に洗えるものが多いですが、ウールは水や熱に弱く、洗濯方法を誤ると縮んだり硬くなったりして、元の風合いを失ってしまいます。洗濯表示は、こうした素材ごとのデリケートな特性を考慮し、「この衣類に最適な手入れは何か」を教えてくれる、いわば道しるべのような存在です。
もし洗濯表示を無視して自己流で手入れをしてしまうと、以下のようなトラブルが発生する可能性があります。
- 縮み・型崩れ: 特にニットやレーヨンなどのデリケートな素材は、不適切な水温や強い機械力で洗うと、目も当てられないほど縮んでしまうことがあります。
- 色落ち・色移り: 濃い色の衣類は、他の淡い色の衣類と一緒に洗うと色が移ってしまうことがあります。洗濯表示には、そうしたリスクを避けるための情報も含まれています。
- 風合いの変化: カシミヤの滑らかさや、シルクの光沢など、素材特有の風合いは非常に繊細です。誤った洗濯や乾燥方法は、これらの美しい質感を損なう原因となります。
- 付属品の破損: ボタンやビーズ、プリント部分なども、強い洗濯や高温のアイロンによって破損したり剥がれたりすることがあります。
これらの失敗は、一度起きてしまうと元に戻すのが非常に困難です。だからこそ、洗濯をする前には必ず洗濯表示を確認する習慣をつけることが大切です。
洗濯表示の目的は、単に「洗濯方法を示す」ことだけではありません。それは、製品を製造したメーカーから消費者への「この服を大切に着てほしい」というメッセージでもあります。作り手は、デザインや素材の選定にこだわり、一着の服を世に送り出します。その服が消費者の手元で最高の状態で長く愛用されることこそ、メーカーにとっての願いです。そのために、最適な取り扱い方法を標準化された記号で伝えるのが洗濯表示の役割です。
消費者側から見ても、洗濯表示を正しく理解することには大きなメリットがあります。高価な衣類や思い入れのある一着を、失敗のリスクなく自分で手入れできるようになれば、クリーニング代の節約につながります。また、衣類を長持ちさせることは、頻繁に買い替える必要がなくなるため、経済的なメリットだけでなく、資源を大切にするサステナブルな消費行動にもつながります。
このように、洗濯表示は私たちの衣生活を支える非常に重要な情報です。次の章では、なぜこの洗濯表示が新しくなったのか、その背景と理由について詳しく見ていきましょう。
洗濯表示が新しくなった理由と変更時期
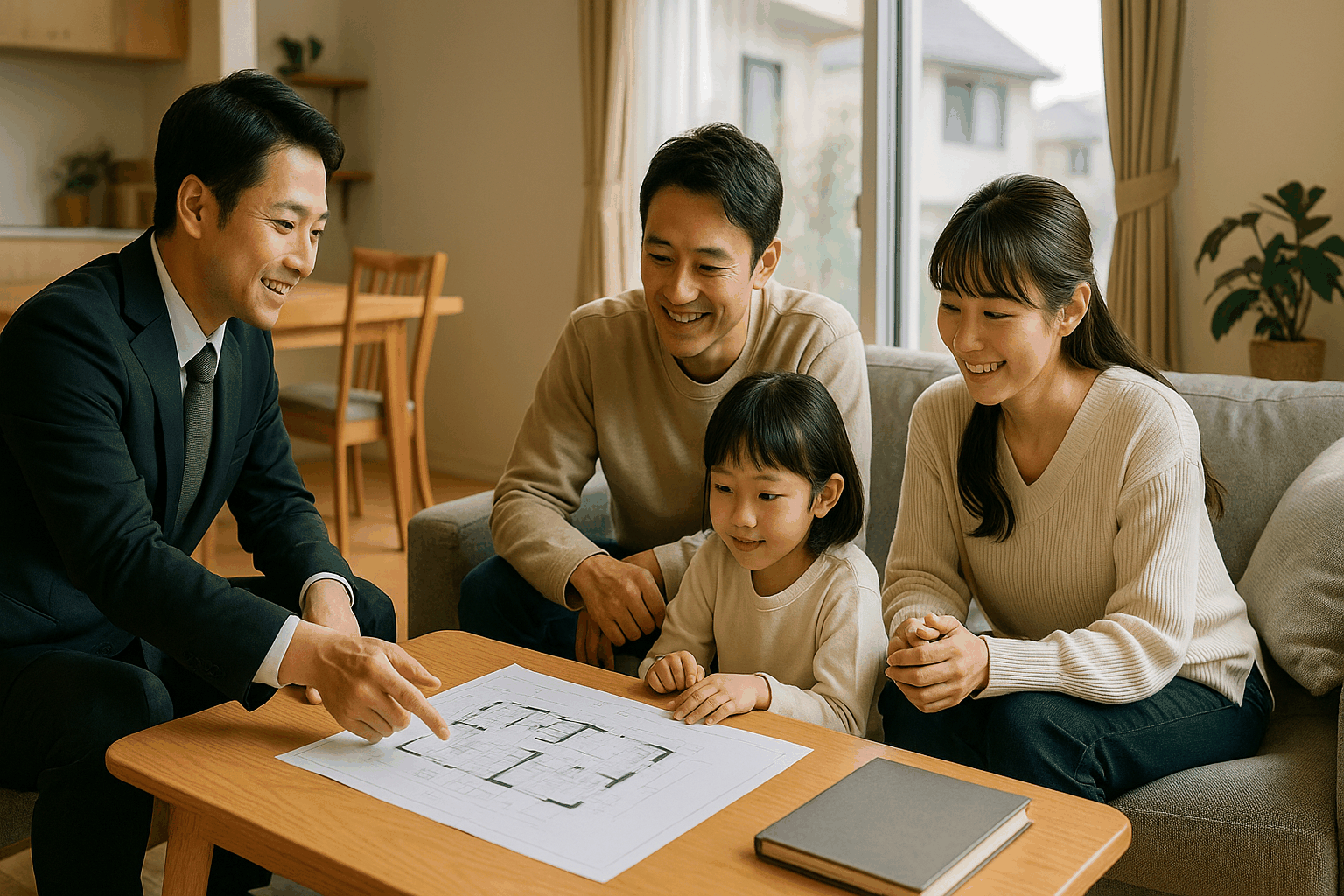
現在私たちが目にしている洗濯表示は、実は数年前に大きく変更されたものです。具体的には、2016年12月1日に、それまでの日本独自の規格(旧JIS)から、国際標準化機構(ISO)が定める国際規格(ISO 3758)に準拠した新しい規格(新JIS)へと完全に移行されました。2016年11月30日までに製造・販売された衣類には旧表示が、同年12月1日以降の製品には新表示が付いています。そのため、クローゼットの中には新旧両方の表示が付いた衣類が混在している可能性があります。
では、なぜわざわざ長年親しまれてきた表示を変更する必要があったのでしょうか。その背景には、私たちのライフスタイルのグローバル化が大きく関係しています。
最大の理由は、洗濯表示を世界共通の基準に統一する必要があったからです。近年、海外のファッションブランドの衣類を国内で購入したり、インターネットを通じて海外から直接衣類を取り寄せたりする機会が格段に増えました。また、海外旅行先で衣類を購入することも珍しくありません。
旧来の日本の洗濯表示は、記号の中に「洗濯機」「手洗イ」「ドライ」「エンソサラシ」といった日本語の文字が入っていたり、日本独自の記号が使われたりしていました。これは日本人にとっては分かりやすい反面、海外の人々には理解が困難でした。逆もまた然りで、日本人が海外で購入した衣類の洗濯表示が理解できず、手入れに困るというケースも多発していました。
このような状況を解消し、国内外のどこで購入した製品であっても、誰もが同じように洗濯表示を理解できるようにすることが、国際規格への移行における最も重要な目的でした。これにより、消費者は製品の国籍を問わず、安心して衣類を購入し、適切に手入れできるようになりました。また、アパレル事業者にとっても、国内外で同じ表示ラベルを使用できるため、生産効率の向上やコスト削減につながるというメリットがあります。
二つ目の理由は、より詳細で的確な情報を提供するためです。旧表示の記号は全部で22種類でしたが、新しい表示では41種類へと大幅に増加しました。これは、衣類の素材や加工技術が多様化・高度化する中で、よりきめ細やかな手入れの情報が必要になったためです。
例えば、新しい表示で追加された記号の代表格に「ウェットクリーニング」があります。これは、ドライクリーニング指定の衣類など、これまで家庭での水洗いが難しいとされてきたものを、クリーニング店が専門的な技術を駆使して水で洗浄する方法です。旧表示にはこの概念がなく、消費者も事業者も混乱することがありました。新しい表示では、ウェットクリーニングが可能か、可能だとしてもどの程度の強さまで耐えられるかを明確に示せるようになり、より適切なクリーニング方法の選択が可能になりました。
また、乾燥方法についても、旧表示では「つり干し」か「平干し」かの大まかな区別しかありませんでした。新表示では、「ぬれたまま干す(ぬれ干し)」や「日陰で干す」といった、より具体的な指示が追加されています。これにより、色あせしやすいデリケートな衣類や、脱水せずに干した方が良い衣類などを、最適な方法で乾燥させることができます。
このように、記号の数を増やすことで、それぞれの衣類が持つ特性に合わせた、より精度の高い情報伝達が可能になったのです。これは、衣類を最高の状態で長持ちさせる上で非常に大きな進歩といえます。
ただし、注意点として、前述の通り2016年11月以前の衣類には旧表示が付いています。古いけれど大切にしている衣類をお持ちの場合、その手入れをする際には旧表示の知識も必要になります。この後、新旧表示の具体的な違いについても解説しますが、まずは新しい表示の基本的なルールをしっかりと理解することが、現代の衣生活における第一歩となります。
洗濯表示の変更は、私たちの生活がよりグローバルになったことの証であり、衣類をより長く、より大切に扱うための進化なのです。次の章では、この新しくなった表示を読み解くための基本的なルールを学んでいきましょう。
新しい洗濯表示の基本的な見方
一見すると複雑に見える新しい洗濯表示ですが、実は非常に論理的なルールに基づいて構成されています。その基本さえ押さえてしまえば、どんな衣類でも表示をスムーズに読み解けるようになります。ここでは、新しい洗濯表示を理解するための2つの重要なポイント、「5つの基本記号」と「付加記号・数字」について解説します。
5つの基本記号を覚える
新しい洗濯表示は、「①家庭洗濯」「②漂白」「③乾燥」「④アイロン仕上げ」「⑤クリーニング」という5つの基本的なカテゴリーに分類されています。そして、衣類のタグには、必ずこの順番で左から右へ記号が並んでいます。 このルールを知っているだけで、記号のグループが何を意味しているのかを直感的に把握できます。
まずは、それぞれのカテゴリーを表す5つの基本記号の形を覚えましょう。
| 基本記号 | カテゴリー | 記号の形 |
|---|---|---|
 |
||
| ① 家庭洗濯 | 洗濯桶の形。家庭での洗濯機洗いや手洗いの方法を示します。 | |
 |
||
| ② 漂白 | 三角形の形。塩素系や酸素系の漂白剤が使えるかどうかを示します。 | |
 |
||
| ③ 乾燥 | 正方形の形。タンブル乾燥(乾燥機)と自然乾燥の方法を示します。 | |
 |
||
| ④ アイロン仕上げ | アイロンの形。アイロンをかける際の適切な温度などを示します。 | |
 |
||
| ⑤ クリーニング | 円形の形。ドライクリーニングやウェットクリーニングの種類を示します。 | |
| (記号画像は消費者庁ウェブサイト「新しい洗濯表示」より引用) |
この5つのプロセスは、私たちが洗濯を行う際の工程順(洗濯→漂白→乾燥→アイロン)に近く、非常に合理的です。クリーニングは家庭での洗濯とは別の選択肢なので、最後に配置されています。
例えば、あるTシャツのタグに「洗濯桶」「三角形」「正方形」「アイロン」「円」の順で記号が並んでいたら、それぞれが家庭洗濯、漂白、乾燥、アイロン、クリーニングに関する指示であるとすぐに判断できます。まずはこの5つの基本形と順番をマスターすることが、新しい洗濯表示を理解するための最も重要な第一歩です。
付加記号と数字が表す意味
5つの基本記号だけでは、大まかなカテゴリーしか分かりません。そこで、より詳細な情報(強さ、温度、禁止など)を伝えるために、「付加記号」と「数字」が組み合わされます。これらの補助的な記号の意味を理解することで、表示の解読精度が一気に高まります。
主な付加記号と数字の役割は以下の通りです。
| 付加記号・数字 | 意味 | 主な使用例 | 解説 |
|---|---|---|---|
| – (下線一本) | 弱い処理 | 洗濯桶、クリーニングの円の下 | 「弱い洗濯」「弱いクリーニング」を意味します。洗濯機の場合は「弱水流コース」や「ソフトコース」などを選びましょう。 |
| = (下線二本) | 非常に弱い処理 | 洗濯桶、クリーニングの円の下 | 「非常に弱い洗濯」「非常に弱いクリーニング」を意味します。洗濯機の場合は「手洗いコース」や「おしゃれ着コース」など、最も優しいコースを選び、洗濯ネットの使用が推奨されます。 |
| ・ (点) | 温度の段階 | アイロン、タンブル乾燥の記号の中 | 点の数が多いほど高温を示します。アイロンでは「・」が低温、「・・」が中温、「・・・」が高温。タンブル乾燥では「・」が低温、「・・」が高温です。 |
| 数字 | 液温の上限(℃) | 洗濯桶の記号の中 | 例えば「40」と書かれていれば、「40℃を上限とする水で洗濯できる」という意味です。この温度を超えると、衣類が傷む原因になります。 |
| × (バツ印) | 禁止 | 全ての基本記号の上 | その操作が「できない」ことを示す、最も強力で分かりやすい記号です。「家庭洗濯不可」「アイロン仕上げ禁止」など、絶対にやってはいけないことを示します。 |
これらの付加記号は、一貫したルールで運用されています。例えば、洗濯桶の下に引かれた横棒は「水流の強さ」を表し、棒がない状態が「普通」、一本が「弱い」、二本が「非常に弱い」となります。この「棒の数で強弱を示す」というルールは、クリーニングの記号(ドライクリーニング、ウェットクリーニング)にも共通して適用されます。
同様に、アイロンの記号の中にある点(・)は「温度」を表し、点の数が多いほど高温に耐えられることを示します。このルールも、タンブル乾燥の記号に共通しています。
そして、すべての基本記号に重ねて表示される「×」は、その行為の「禁止」を意味します。洗濯桶にバツがあれば「家庭洗濯不可」、アイロンにバツがあれば「アイロン仕上げ禁止」となり、非常に直感的で理解しやすい記号です。
このように、新しい洗濯表示は、「5つの基本記号(カテゴリー)」をベースに、「付加記号と数字(詳細な条件)」を組み合わせることで、41種類もの詳細な情報を体系的に表現しています。この構造を理解すれば、未知の記号が出てきても、基本ルールに立ち返って意味を推測することが可能になります。次の章では、これらのルールを元に、全41種類の記号をカテゴリー別に詳しく見ていきましょう。
【一覧】新しい洗濯表示の記号と意味
ここからは、新しい洗濯表示の全41種類の記号を、5つの基本カテゴリー「家庭での洗濯方法」「漂白方法」「乾燥方法」「アイロンのかけ方」「クリーニングの種類」に分けて、一覧表と解説で詳しく見ていきます。お手元の衣類のタグと見比べながら確認してみてください。
家庭での洗濯方法
家庭での洗濯方法は「洗濯桶」の記号で示されます。桶の中の数字は「液温の上限」、桶の下の横線は「洗濯の強さ」を表します。
| 記号 | 意味と解説 |
|---|---|
 |
|
| 液温は95℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる 最も強い条件での洗濯が可能です。主に業務用のリネン類(シーツ、白衣など)に見られます。 |
|
| 液温は70℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる 高温での洗濯が可能な、丈夫な綿素材などに使われます。 |
|
 |
|
| 液温は60℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる 白い綿製品など、熱に強く衛生的に洗いたい衣類に見られます。 |
|
 |
|
| 液温は50℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる 一般的なポリエステルや綿製品など、比較的丈夫な衣類に適用されます。 |
|
 |
|
| 液温は40℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる 最も一般的な表示の一つ。多くのTシャツやシャツ、普段着に見られます。 |
|
 |
|
| 液温は40℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる 下の横線一本は「弱い力」を示します。洗濯機の「弱水流」「ソフト」「ドライ」などのコースを選びましょう。 |
|
 |
|
| 液温は40℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯ができる 下の横線二本は「非常に弱い力」を示します。おしゃれ着やデリケートな素材に使われ、「手洗いコース」など最も優しいコースを選び、洗濯ネットの使用が強く推奨されます。 |
|
 |
|
| 液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる 低温での洗濯が推奨される衣類です。 |
|
 |
|
| 液温は30℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる デリケートな素材で、かつ低温での洗濯が必要な場合に表示されます。 |
|
| 液温は30℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯ができる ウールやレーヨンなど、特に繊細な扱いの必要な衣類に見られます。 |
|
 |
|
| 液温は40℃を限度とし、手洗いができる 洗濯桶に手を入れているこの記号は、手洗いを推奨するものです。洗濯機の手洗いコースも使用可能ですが、優しく押し洗いするのが基本です。 |
|
 |
|
| 家庭での洗濯禁止 この表示がある場合は、家庭の洗濯機でも手洗いでも洗濯できません。クリーニングの表示を確認し、専門家に任せましょう。 |
|
| (記号画像は消費者庁ウェブサイト「新しい洗濯表示」より引用) |
漂白方法
漂白方法は「三角形」の記号で示されます。漂白剤には、色柄物にも使える「酸素系」と、白物専用で効果が強い「塩素系」があります。間違えると色落ちの原因になるため、必ず確認しましょう。
| 記号 | 意味と解説 |
|---|---|
 |
|
| 塩素系及び酸素系の漂白剤を使用して漂白ができる 白無地の三角形は、どちらの種類の漂白剤も使用可能であることを示します。 |
|
 |
|
| 酸素系の漂白剤のみ使用できる 三角形に斜線が入っている場合、塩素系漂白剤は使用できません。色柄物の衣類の多くがこの表示に該当します。誤って塩素系を使うと、色が抜けてしまうので注意が必要です。 |
|
 |
|
| 塩素系及び酸素系の漂白剤の使用禁止 三角形にバツ印がある場合は、いかなる漂白剤も使用できません。 |
|
| (記号画像は消費者庁ウェブサイト「新しい洗濯表示」より引用) |
乾燥方法
乾燥方法は「正方形」の記号で示され、「タンブル乾燥」と「自然乾燥」の2種類に大別されます。
タンブル乾燥
タンブル乾燥とは、乾燥機の中で衣類を回転させながら温風を当てて乾かす方法です。正方形の中に円が描かれているのが目印です。熱に弱い素材や縮みやすい衣類は禁止されていることが多いので、特に注意が必要です。
| 記号 | 意味と解説 |
|---|---|
 |
|
| タンブル乾燥ができる(排気温度上限80℃) 円の中の点が2つは高温設定を示します。タオルや丈夫な綿製品などに使われます。 |
|
 |
|
| 低温でのタンブル乾燥ができる(排気温度上限60℃) 円の中の点が1つは低温設定を示します。高温に弱い化学繊維などに使われます。 |
|
 |
|
| タンブル乾燥禁止 ニットやデリケートな素材に多い表示です。これを無視すると、衣類が著しく縮んだり傷んだりする原因になります。 |
|
| (記号画像は消費者庁ウェブサイト「新しい洗濯表示」より引用) |
自然乾燥
物干し竿やハンガーにかける自然乾燥は、正方形の中に線が描かれている記号で示されます。線の種類で「干し方」、左上の斜線で「日光に当てて良いか」が分かります。
| 記号 | 意味と解説 |
|---|---|
 |
|
| つり干しがよい ハンガーや物干し竿にかけて干す、最も一般的な干し方です。 |
|
 |
|
| 日陰のつり干しがよい 左上の斜線は「日陰」を示します。紫外線による色あせや黄ばみを防ぎたい衣類(濃い色のもの、絹製品など)に適用されます。 |
|
 |
|
| ぬれつり干しがよい 縦線が2本ある場合は、洗濯機で脱水せず、濡れたままの状態で干すことを意味します。しわを防ぎたい麻やレーヨンのシャツなどに適しています。 |
|
| 日陰でのぬれつり干しがよい 「ぬれ干し」と「日陰干し」を組み合わせた指示です。 |
|
 |
|
| 平干しがよい 横線は平干し台などの上に平らに置いて干すことを示します。ニットやセーターなど、水の重みで伸びたり型崩れしたりしやすい衣類に必須の干し方です。 |
|
 |
|
| 日陰の平干しがよい 「平干し」と「日陰干し」を組み合わせた指示です。色の濃いニット製品などに使われます。 |
|
 |
|
| ぬれ平干しがよい 脱水せずに濡れたまま平干しします。 |
|
 |
|
| 日陰でのぬれ平干しがよい 最もデリケートな干し方の一つです。 |
|
| (記号画像は消費者庁ウェブサイト「新しい洗濯表示」より引用) |
アイロンのかけ方
アイロンのかけ方は、そのまま「アイロン」の形で示されます。中の点の数で温度の上限が分かります。
| 記号 | 意味と解説 |
|---|---|
 |
|
| 底面温度200℃を限度としてアイロン仕上げができる 点が3つは高温設定。綿や麻などの熱に強い素材に使われます。 |
|
 |
|
| 底面温度150℃を限度としてアイロン仕上げができる 点が2つは中温設定。ウールやポリエステル、レーヨンなどに適しています。あて布が必要な場合が多いです。 |
|
 |
|
| 底面温度110℃を限度としてアイロン仕上げができる 点が1つは低温設定。ナイロン、アクリル、ポリウレタンなど熱に弱い化学繊維に使われます。スチームは使用できません。 |
|
 |
|
| スチームアイロンの使用禁止 この記号は単独では存在せず、上記のいずれかのアイロン記号と組み合わせて表示されることがあります。 |
|
 |
|
| アイロン仕上げ禁止 アイロンにバツ印がある場合は、アイロンがけはできません。 |
|
| (記号画像は消費者庁ウェブサイト「新しい洗濯表示」より引用) |
クリーニングの種類
家庭での洗濯が難しい衣類のためのクリーニングは「円」の記号で示されます。専門家であるクリーニング店向けの指示ですが、知っておくとどの店に出すべきか判断する助けになります。
ドライクリーニング
ドライクリーニングは、水を使わず有機溶剤で汚れを落とす洗濯方法です。水洗いすると型崩れや縮みを起こしやすいウール製品やスーツ、コートなどに用いられます。円の中のアルファベットは、使用できる溶剤の種類を示しています。
| 記号 | 意味と解説 |
|---|---|
 |
|
| パークロロエチレン及び石油系溶剤によるドライクリーニングができる 「P」は、ほとんどの溶剤が使えることを示します。 |
|
 |
|
| パークロロエチレン及び石油系溶剤による弱いドライクリーニングができる 下の横線一本は「弱い処理」を意味します。 |
|
 |
|
| 石油系溶剤によるドライクリーニングができる 「F」は、よりデリケートな石油系溶剤のみ使用可能であることを示します。 |
|
 |
|
| 石油系溶剤による弱いドライクリーニングができる 「F」指定で、かつ「弱い処理」が必要なデリケートな衣類です。 |
|
| ドライクリーニング禁止 円にバツ印、かつ中の文字が「DRY」でない場合は、ドライクリーニングができないことを示します。 |
|
| (記号画像は消費者庁ウェブサイト「新しい洗濯表示」より引用) |
ウェットクリーニング
ウェットクリーニングは、クリーニング店が専門的な知識と技術を用いて水洗いと仕上げを行う方法です。ドライクリーニングでは落ちにくい汗などの水溶性の汚れを落とすのに適しています。旧表示にはなかった、新しいクリーニング方法です。
| 記号 | 意味と解説 |
|---|---|
 |
|
| ウェットクリーニングができる 円の中に「W」(Wet)がある記号です。プロによる水洗いが可能です。 |
|
 |
|
| 弱い操作によるウェットクリーニングができる 下の横線一本は「弱い処理」を意味します。 |
|
| 非常に弱い操作によるウェットクリーニングができる 下の横線二本は「非常に弱い処理」を意味し、極めて慎重な作業が求められます。 |
|
 |
|
| ウェットクリーニング禁止 この表示がある衣類は、プロによる水洗いもできません。 |
|
| (記号画像は消費者庁ウェブサイト「新しい洗濯表示」より引用) |
旧洗濯表示との主な違い
2016年12月1日を境に切り替わった新しい洗濯表示。クローゼットに眠っている古い衣類や、長く愛用している一着には、今となっては懐かしい「旧洗濯表示」が付いているはずです。新しい表示に慣れてきた今だからこそ、旧表示との違いを改めて確認することで、両方の表示をスムーズに理解できるようになります。
ここでは、新旧の洗濯表示の主な違いを4つのポイントに絞って解説します。
1. 記号のデザインと構成の全面的な変更
最も大きな違いは、記号のデザインそのものです。旧表示は、洗濯機の絵や「手洗イ」といった日本語の文字、そして「高・中・低」などの漢字表記が記号内に含まれており、日本人にとっては直感的で分かりやすいものでした。
| 旧表示の例 | 新表示の例 | 変更点のポイント |
|---|---|---|
 |
||
 |
||
| 洗濯機の絵がなくなり、シンプルな洗濯桶の記号に統一。液温上限の「40」は桶の中に表示され、強弱は桶の下の横線一本(弱い)で表現。 | ||
 |
||
| 「手洗イ」の文字が消え、桶に手を入れる記号に変更。液温上限は原則40℃に統一されたため、記号内に数字は表示されません。 | ||
 |
||
| 温度を示す「中」の文字がなくなり、点の数(二つで中温)で表現。「あて布」の指示は記号から分離され、記号の近くに付記用語として日本語で記載される形になりました。 | ||
| (記号画像は消費者庁ウェブサイト「新しい洗濯表示」より引用) |
このように、新表示は文字情報を極力排除し、世界共通のピクトグラム(絵文字)で情報を伝える形式にシフトしました。これにより、言語の壁を越えて意味が伝わるようになったのです。
2. 記号の種類が22種類から41種類へ大幅に増加
情報量を増やすことも、変更の大きな目的でした。旧表示の22種類では伝えきれなかった、より細かな手入れ方法を伝えるために、新表示では記号の数がほぼ倍増の41種類になりました。
特に大きく拡充されたのが「乾燥」と「クリーニング」のカテゴリーです。
- 乾燥方法の細分化: 旧表示では「つり干し」と「平干し」程度しかありませんでしたが、新表示ではこれに「ぬれ干し」や「日陰干し」の概念が加わり、8種類の自然乾燥記号ができました。さらに、旧表示では一つの記号だったタンブル乾燥も、新表示では高温と低温の区別がされるようになり、より安全な乾燥が可能になりました。
- 「ウェットクリーニング」の追加: 前述の通り、旧表示にはなかったプロによる水洗い「ウェットクリーニング」の記号(円にW)が新設されました。これにより、ドライクリーニングだけでは落とせない汗汚れなどに対応できる衣類であることが、明確に示せるようになりました。
この情報量の増加により、消費者はより衣類の状態に適した、失敗の少ない手入れを選択できるようになりました。
3. 「絞り方」の記号の廃止
旧表示には、「手絞りは弱く」や「絞ってはいけない」といった、絞り方に関する独立した記号が存在しました。
しかし、新表示ではこれらの記号は廃止されました。では、絞り方の情報はどこへ行ったのでしょうか。実は、家庭洗濯の記号(洗濯桶)がその役割を兼ねることになりました。
- 桶の下に横線なし(普通): 通常の強さで絞って良い(遠心脱水が可能)。
- 桶の下に横線一本(弱い): 弱く絞る(遠心脱水は短時間で)。
- 桶の下に横線二本(非常に弱い): 非常に弱く絞るか、絞ってはいけない場合もある(遠心脱水は不可またはごく短時間)。
- ぬれ干しの記号: 脱水せずに干すことを意味するため、実質的に「絞ってはいけない」という指示になります。
このように、絞り方の強弱は洗濯全体の強弱の中に含まれる、という考え方に整理されたのです。
4. 付記用語の役割の変化
旧表示では「あて布」「ネット使用」といった推奨事項が、記号の近くに比較的自由に書かれていました。新表示でもこの「付記用語」は存在しますが、その役割がより明確化されています。
新表示では、記号だけでは伝えきれない補足的な情報を、記号の近傍に日本語で記載することになっています。例えば、以下のような情報が付記されます。
- 「洗濯ネット使用」
- 「あて布使用」
- 「単独洗い」
- 「裏返して洗う」
- 「付属品は取り外して洗う」
これらの付記用語は、記号が示す基本的な指示に加えて、より美しく、より安全に衣類を保つための重要なアドバイスです。洗濯表示を確認する際は、記号本体だけでなく、この付記用語までしっかりと目を通す習慣をつけましょう。
これらの違いを理解することで、古い衣類も新しい衣類も、それぞれの表示が持つ意味を正しく読み取り、適切に手入れすることができるようになります。
洗濯表示に関するよくある質問
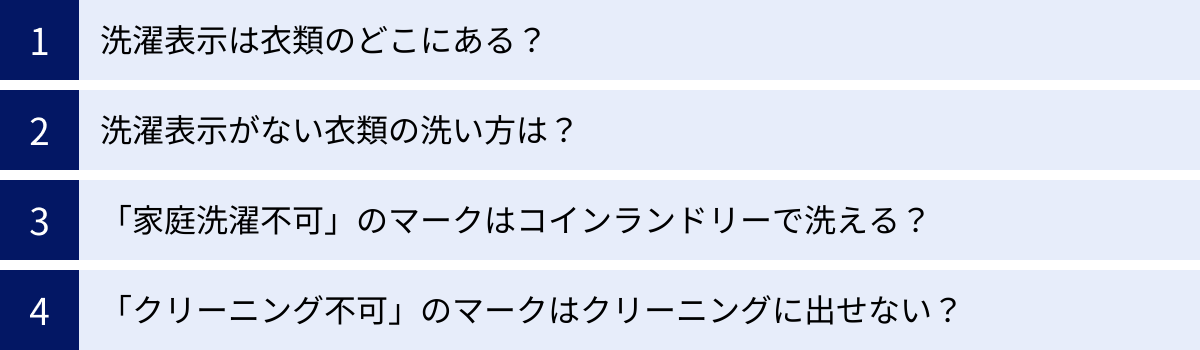
新しい洗濯表示について学んできましたが、実際の洗濯シーンでは「これはどうなんだろう?」と迷う場面も出てくるでしょう。ここでは、多くの人が疑問に思う点をQ&A形式で解説していきます。
洗濯表示は衣類のどこにある?
洗濯表示は、通常、衣類の内側に縫い付けられた白い布製のラベル(品質表示タグ)に印字されています。見つけやすい場所は以下の通りです。
- トップス(Tシャツ、シャツ、セーターなど):
- 左脇の内側の縫い目: 最も一般的な場所です。服をめくって脇の下あたりを探してみてください。
- 襟首の後ろ: ブランドタグと一緒についている場合もあります。
- ボトムス(パンツ、スカートなど):
- 腰(ウエスト)の内側、後ろ中心または左脇: ベルトラインの内側を確認してみましょう。
- アウター(ジャケット、コートなど):
- 左脇の内側: トップスと同様です。
- 内ポケットの中: ポケットの内部にタグが隠されていることもあります。
- 下着や靴下:
- デリケートな製品や小さな製品では、肌触りを考慮してタグを付けず、パッケージに表示が記載されていたり、生地自体にプリントされていたりする場合があります。購入時に確認し、必要であれば写真を撮っておくと良いでしょう。
この品質表示タグには、洗濯表示の他に、「繊維の組成(素材)」「製造・販売元の社名と連絡先」なども記載されています。万が一、洗濯でトラブルが起きた際に問い合わせるためにも、このタグは切り取らずに保管しておくことが重要です。
洗濯表示がない衣類の洗い方は?
古着やハンドメイド品、海外のお土産などで、洗濯表示タグ自体が付いていない衣類に出会うことがあります。この場合、洗濯は完全に自己責任となりますが、以下の手順でリスクを最小限に抑えながら試すことができます。
- 素材を推測する: まずは、その衣類が何でできているかを見極めます。見た目や手触りから、綿、麻、ポリエステル、ウール、シルクなどの素材を推測します。光沢があればシルクやレーヨン、ごわごわしていれば麻、暖かみがあればウールといった具合です。もし組成表示だけでも残っていれば、それが最大のヒントになります。
- 色落ちテストを行う: 洗濯で最も怖い失敗の一つが色落ちです。これを防ぐため、必ず事前にテストをしましょう。
- 白い布やコットンに、洗濯で使う予定の液体洗剤を少量つけます。
- 衣類の縫い代や裾の裏側など、目立たない部分を、その布で軽く叩きます。
- 数分置いて、白い布に色が移っていないか確認します。もし色が移るようであれば、必ず単独で洗う必要があります。
- 最も安全な方法で洗う: テストで問題がなくても、最初は最も衣類に優しい方法で洗うのが鉄則です。
- 洗剤: おしゃれ着洗い用の中性洗剤を選びます。
- 水温: 水または30℃以下のぬるま湯を使います。
- 洗い方: 洗面器などで優しく「押し洗い」し、決してゴシゴシこすらないようにします。すすぎも同様に優しく行います。
- 脱水: タオルで挟んで水気を吸い取る「タオルドライ」が最も安全です。洗濯機で脱水する場合は、15秒~30秒程度のごく短い時間にとどめましょう。
- 干し方: 型崩れしにくい「平干し」か、形を整えてからの「日陰のつり干し」が無難です。
- 迷ったらプロに相談: 大切な衣類や高価な衣類で、どうしても自分で洗うのが不安な場合は、迷わずクリーニング店に相談しましょう。プロは素材や状態を見て、最適な方法を提案してくれます。
「家庭洗濯不可」のマークはコインランドリーで洗える?
答えは「No」です。絶対に洗ってはいけません。
「家庭洗濯不可」(洗濯桶にバツ印)のマークは、「家庭で行う洗濯(水洗い)全般を禁止する」という意味です。これには、自宅の洗濯機や手洗いはもちろん、コインランドリーでの洗濯も含まれます。
コインランドリーの洗濯機は家庭用よりも大型でパワフルなものが多いため、「家庭洗濯不可」のデリケートな衣類を洗ってしまうと、以下のような深刻なダメージを引き起こす可能性が非常に高いです。
- 激しい縮みや型崩れ: ウールやレーヨンなどの素材は、元に戻らないほど変形してしまう恐れがあります。
- 風合いの著しい劣化: カシミヤの柔らかさやシルクの光沢などが失われ、ゴワゴワになってしまうことがあります。
- コーティングや加工の剥がれ: 特殊な加工が施された衣類は、その機能性が失われる原因になります。
- 他の衣類へのダメージ: 万が一、洗った衣類から部品が取れたり色が移ったりすると、一緒に洗っている他の利用者の衣類にまで被害が及ぶ可能性があります。
「家庭洗濯不可」の表示がある衣類は、必ずタグの右側にある「クリーニング」の表示を確認し、ドライクリーニングかウェットクリーニングが可能な場合は、クリーニング店に依頼してください。
「クリーニング不可」のマークはクリーニングに出せない?
円にバツ印が描かれた「クリーニング不可」のマーク。これは、「ドライクリーニングもウェットクリーニングも、どちらも推奨できません」というメーカーからのメッセージです。
この表示がある衣類は、革製品や合成皮革、特殊な装飾が施されたものなど、クリーニング溶剤や水に非常に弱い素材で作られている場合がほとんどです。そのため、原則としてクリーニング店に持ち込んでも断られてしまうケースが多いでしょう。
しかし、完全に諦める必要はありません。
クリーニング店の中には、豊富な知識と特殊な技術を持つ「腕の良い」店や、難しいとされる衣類を専門に扱う店が存在します。そうした店では、表示上は不可となっていても、職人の判断と技術で汚れを落としてくれる場合があります。例えば、部分的なシミ抜きや、特殊な溶剤を使わない手作業での洗浄など、その衣類に合わせたオーダーメイドの対応を検討してくれるかもしれません。
もし「クリーニング不可」でも手入れをしたい大切な衣類がある場合は、
- 複数のクリーニング店に相談してみる。
- 衣類を購入した店に、推奨される手入れ方法を問い合わせてみる。
- レザー専門、ドレス専門など、その衣類のジャンルに特化したクリーニング業者を探してみる。
といった方法を試す価値はあります。ただし、その場合もリスクが伴うことを理解し、クリーニング店とよく相談した上で依頼することが重要です。
洗濯表示を正しく理解して衣類を長持ちさせよう
この記事では、2016年から新しくなった洗濯表示について、その背景から基本的な見方、全41種類の記号の意味、そして多くの人が抱える疑問まで、包括的に解説してきました。
複雑に見えた新しい洗濯表示も、「5つの基本記号」と「付加記号」のルールさえ理解すれば、誰でも論理的に読み解けることがお分かりいただけたかと思います。新しい表示は、単なるデザインの変更ではなく、グローバル化する私たちの生活に対応し、より多様化・繊細化する衣類を適切に手入れするための、必然的な進化でした。
洗濯表示は、お気に入りの一着をできるだけ長く、美しい状態のまま楽しむための、最も信頼できるガイドブックです。毎回洗濯する前に、ほんの少し時間を使ってタグを確認する。この小さな習慣が、取り返しのつかない洗濯の失敗を防ぎ、結果的に経済的な節約やサステナブルな消費行動にもつながります。
家庭で洗えるのか、クリーニングに出すべきなのか。漂白剤は使えるのか。乾燥機はOKか。アイロンの温度は何度が最適か。――その答えは、すべてタグの中にあります。
今日から、クローゼットの中の衣類のタグを改めて見直してみてください。そして、新しく衣類を購入する際には、デザインや価格だけでなく、洗濯表示にも目を通して「家で手入れできるか」を確認する癖をつけることをおすすめします。
洗濯表示を正しく理解し、味方につけること。それこそが、賢い消費者として、大切な衣類と長く付き合っていくための第一歩です。この記事が、あなたのこれからの豊かな衣生活の一助となれば幸いです。
参照:消費者庁「新しい洗濯表示」ウェブサイト