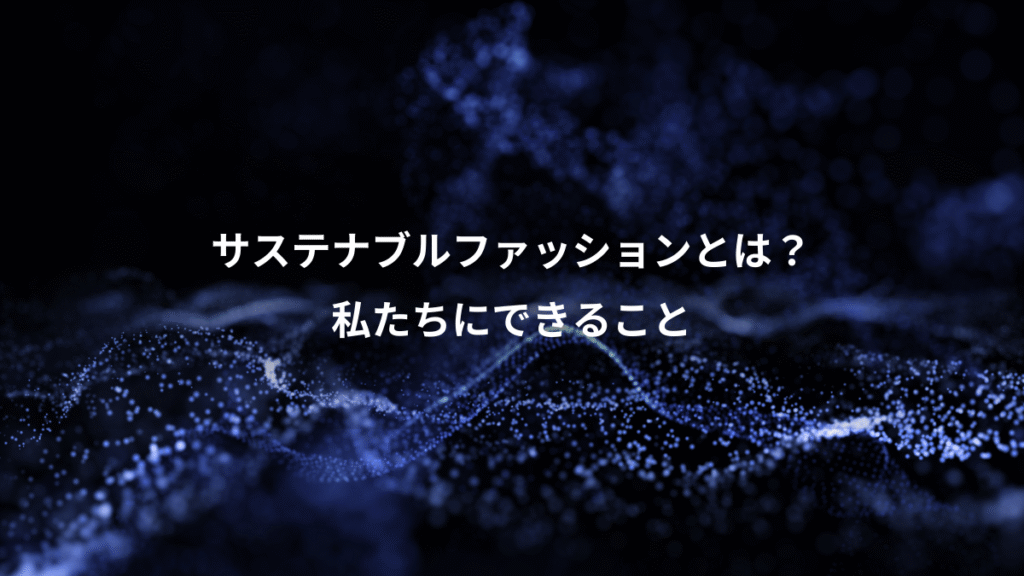近年、ファッション業界において「サステナブル」という言葉を耳にする機会が急激に増えました。雑誌やウェブメディア、店頭でも頻繁に見かけるこの言葉ですが、その正確な意味や背景、そして私たち消費者に何ができるのかを深く理解している人はまだ少ないかもしれません。
この記事では、「サステナブルファッション」とは何かという基本的な定義から、なぜ今これほどまでに注目されているのかという社会的な背景、そして具体的な取り組みや私たち一人ひとりが実践できるアクションまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。
この記事を読み終える頃には、サステナブルファッションが単なるトレンドではなく、これからの時代における新しいファッションの楽しみ方であり、より良い未来を築くための重要な選択肢であることが理解できるでしょう。日々の洋服選びが、地球環境や社会貢献に繋がる。そんな新しい視点を得るきっかけにしてください。
目次
サステナブルファッションとは?
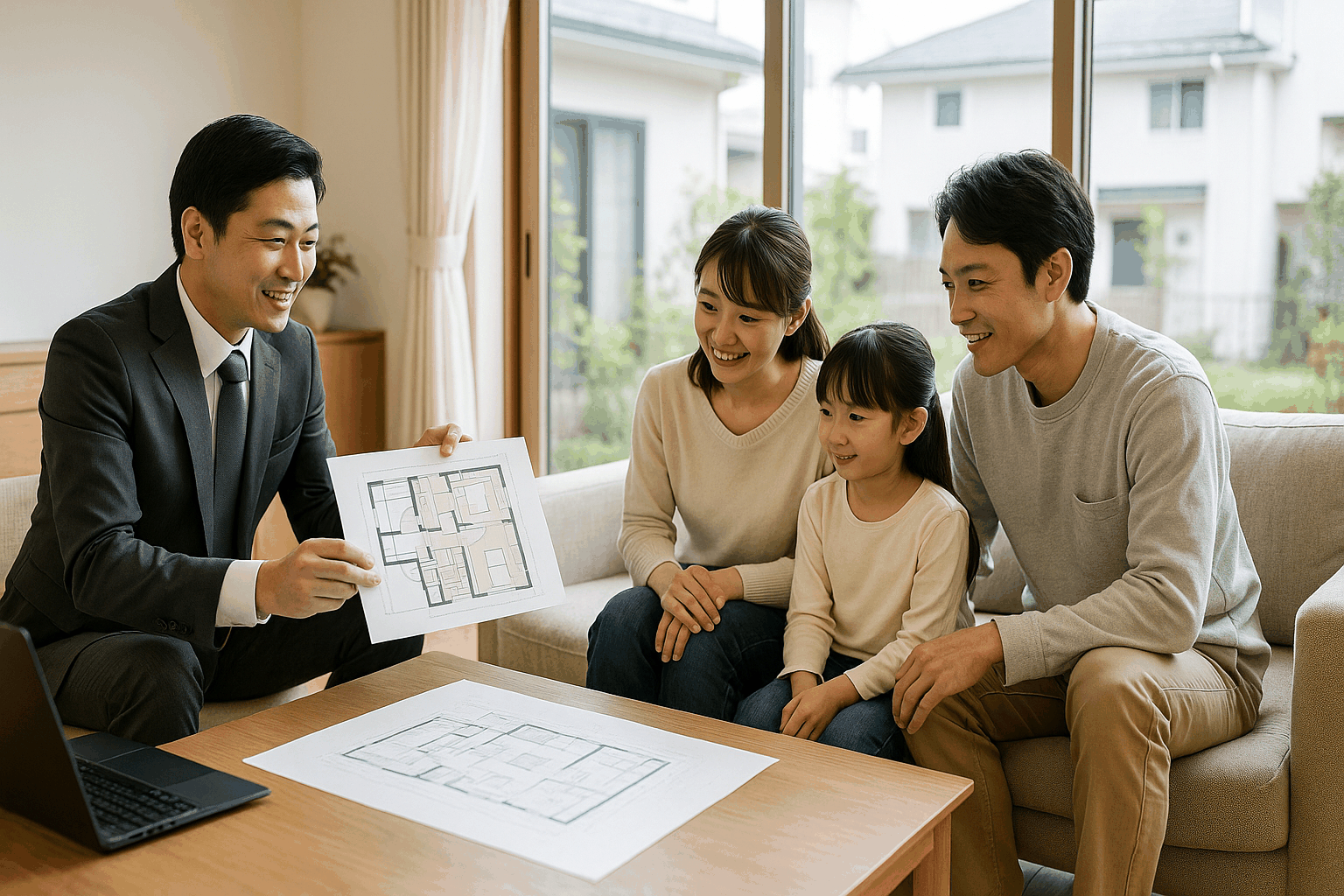
まず初めに、「サステナブルファッション」という言葉の基本的な意味と、関連する用語との違いについて掘り下げていきましょう。この概念を正しく理解することが、今後のファッションとの向き合い方を考える上で最初の重要なステップとなります。
地球環境や社会に配慮したファッションのこと
サステナブルファッションとは、直訳すると「持続可能なファッション」を意味します。ここでの「持続可能(サステナブル)」とは、地球の環境や社会的な側面において、将来の世代が必要とするものを損なうことなく、現代の私たちのニーズを満たすという考え方です。
これをファッションの世界に当てはめると、衣服の原料調達から、企画、生産、輸送、販売、そして消費者が着用し、最終的に廃棄するまでの一連のライフサイクル全体において、環境への負荷を可能な限り低減し、関わるすべての人々の人権や労働環境に配慮したファッションのあり方を指します。
具体的には、以下のような多岐にわたる要素が含まれます。
- 環境への配慮:
- 農薬や化学肥料の使用を抑えたオーガニック素材や、ペットボトルなどを再利用したリサイクル素材の採用。
- 生産過程での水の使用量やCO2排出量の削減。
- 染色工程での有害な化学物質の使用を避け、水質汚染を防ぐ取り組み。
- 過剰な生産を抑制し、売れ残った衣類の大量廃棄をなくすこと。
- 動物の毛皮(リアルファー)など、動物福祉を損なう素材を使用しないこと。
- 社会への配慮:
- 生産工場で働く人々に対して、安全で衛生的な労働環境を提供すること。
- 不当な低賃金や長時間労働、児童労働などをなくし、生活を維持できる正当な対価(リビングウェイジ)を支払うこと。
- 発展途上国の生産者と公正な価格で取引を行う「フェアトレード」の推進。
- 伝統的な技術や文化を尊重し、継承していくこと。
このように、サステナブルファッションは単に「エコな素材を使った服」という狭い意味に留まりません。地球環境の保全(Planet)、社会的な公正(People)、そして経済的な持続性(Profit)という3つの側面を統合し、ファッション産業全体をより健全で持続可能なものへと変革していくことを目指す、包括的な概念なのです。
エシカルファッションとの違い
サステナブルファッションと非常によく似た言葉に「エシカルファッション」があります。この二つは多くの点で重なり合っており、しばしば同義語として使われることもありますが、そのニュアンスには少し違いがあります。
エシカル(Ethical)とは「倫理的な、道徳的な」という意味です。つまり、エシカルファッションは、法律などのルールだけでなく、良識や道徳観に基づき、人や社会、地球環境、動物に対して正しく配慮しようという考え方を重視したファッションを指します。
両者の違いと共通点を整理すると、以下の表のようになります。
| 観点 | サステナブルファッション | エシカルファッション |
|---|---|---|
| 中核となる概念 | 持続可能性(環境・社会・経済のバランスを保ち、将来にわたって継続できること) | 倫理・道徳(人、社会、環境、動物に対して正しくあるべきという良心的な考え) |
| 主な焦点 | 環境負荷の低減、資源の循環、CO2排出削減、長期的なシステム構築 | 人権擁護、公正な取引(フェアトレード)、動物福祉(アニマルウェルフェア)、労働環境の改善 |
| 時間的な視点 | 未来志向。将来の世代への影響を強く意識する。 | 現在志向。今ここにある不正や問題に対して、倫理的に正しい行動をすることを重視する。 |
| 共通点 | どちらも地球環境や社会全体をより良くすることを目指しており、具体的な取り組み(オーガニック素材の利用、フェアトレードなど)は大きく重なり合う。 |
簡単に言えば、サステナブルファッションが「未来に向けて続けられるか?」という時間軸の視点を強く持つのに対し、エシカルファッションは「その行いは道徳的に正しいか?」という倫理的な判断基準に重きを置く傾向があります。
例えば、生産過程で大量のCO2を排出する方法は、地球温暖化を加速させ未来の環境を損なうため「サステナブルではない」と判断されます。一方、発展途上国の労働者に不当な低賃金を強いることは、人道的な観点から「エシカルではない」と判断されます。
しかし、実際にはこれらは密接に絡み合っています。劣悪な労働環境は社会の持続可能性を損ないますし、環境破壊は人々の生活を脅かす倫理的な問題でもあります。
したがって、両者を厳密に区別することに固執する必要はありません。「サステナブル」と「エシカル」は、互いを補完し合う関係にあり、どちらも「人、社会、地球に優しいファッション」という大きな目標を共有しています。この記事では、これらを包括する広い意味での「サステナブルファッション」として話を進めていきます。
なぜ今サステナブルファッションが注目されているのか
サステナブルファッションは、一部の意識の高い人々だけのものではなく、今やファッション業界全体、そして世界中の消費者が無視できない大きな潮流となっています。では、なぜこれほどまでに注目を集めるようになったのでしょうか。その背景には、現代のファッション産業が抱える深刻な環境問題と人権問題が存在します。
ファッション業界が抱える環境問題
きらびやかで華やかなイメージの裏で、ファッション産業は地球環境に極めて大きな負荷をかけている産業の一つです。特に、2000年代以降に主流となった「ファストファッション」の拡大が、その問題を深刻化させました。
大量生産と大量廃棄
ファストファッションは、最新のトレンドをいち早く取り入れたデザインの衣類を、驚くほど短いサイクルで、かつ安価に提供するビジネスモデルです。消費者は気軽に流行の服を手に入れられるようになりましたが、その裏側では「作っては捨て、また作る」という負の連鎖が加速しています。
- 驚異的な生産量:世界の衣料品の生産量は、2000年から2014年の間に約2倍に増加したと報告されています。これは、消費者が購入する衣類の数が劇的に増えたことを意味します。(参照:Ellen MacArthur Foundation “A new textiles economy: Redesigning fashion’s future”)
- 短い着用回数と大量廃棄:安価に手に入るため、多くの服が「使い捨て」のように扱われ、1着あたりの平均着用回数は著しく減少しました。結果として、まだ着られる状態の服も含む大量の衣類がゴミとして廃棄されています。環境省の調査によると、日本では年間に約51万トンの衣類が家庭から手放され、そのうち約65%にあたる約33万トンが焼却・埋め立て処分されています。これは、1日あたりに換算すると、大型トラック約90台分もの衣類が毎日捨てられている計算になります。(参照:環境省「サステナブルファッション」)
- 焼却・埋め立てによる環境負荷:焼却処分はCO2を排出し地球温暖化を促進します。また、ポリエステルなどの化学繊維は、埋め立てられても自然分解されるのに数百年以上かかると言われ、土壌汚染の原因となります。
このように、流行を追い求めるあまりに加速した大量生産・大量消費・大量廃棄のサイクルが、地球の資源を無駄遣いし、深刻なゴミ問題を引き起こしているのです。
生産過程での水質汚染と水の大量消費
私たちが普段何気なく着ている一枚の服を作るために、膨大な量の水が使われ、そして汚染されているという事実も、大きな問題です。
- 水の大量消費:特に、Tシャツなどによく使われるコットン(綿)の栽培には、非常に多くの水が必要です。一般的なコットンTシャツを1枚作るのに、約2,700リットルの水が必要だと言われています。これは、一人の人間が飲む水の量に換算すると約3年分に相当する量であり、水不足が深刻な地域での栽培は、地域住民の生活を脅かすことにも繋がります。(参照:世界自然保護基金(WWF)ジャパン)
- 農薬による土壌・水質汚染:コットンの栽培では、害虫駆除のために大量の殺虫剤や農薬が使われることが多く、これが土壌や周辺の河川を汚染し、生態系や農家の健康に悪影響を及ぼすケースが報告されています。
- 染色工程での水質汚染:生地を様々な色に染める工程では、多くの化学染料や薬品が使用されます。発展途上国の一部の工場では、この染色後の汚水が適切な処理をされないまま河川に排出されることがあります。これにより、川の水が飲めなくなるだけでなく、川の生き物が生息できなくなり、地域の生態系が破壊されるという深刻な事態を引き起こしています。
- マイクロプラスチック問題:ポリエステルやフリースなどの化学繊維でできた衣類を洗濯すると、目に見えないほど小さなプラスチックの繊維(マイクロファイバー)が抜け落ち、下水を通じて最終的に海へと流れ着きます。このマイクロプラスチックは、海洋生物が餌と間違えて摂取することで生態系に悪影響を与えるだけでなく、食物連鎖を通じて人間の体内にも取り込まれる可能性が懸念されています。
CO2の大量排出
ファッション産業は、地球温暖化の原因となる二酸化炭素(CO2)の排出量が非常に多い産業としても知られています。
国連環境計画(UNEP)によると、ファッション産業は世界の温室効果ガス排出量の約8〜10%を占めていると推定されており、これは国際航空業界と海運業界を合わせた排出量を上回るほどの規模です。(参照:UNEP “Act Now for a Better Fashion Industry”)
CO2は、衣類のライフサイクルのあらゆる段階で排出されています。
- 原料生産:特にポリエステルなどの化学繊維は、石油を原料としており、その製造過程で多くのエネルギーを消費し、大量のCO2を排出します。
- 紡績・縫製:工場を稼働させるための電力消費。
- 輸送:原材料や製品を世界中に輸送するための航空機や船舶の利用。
- 販売・消費:店舗の照明や空調、消費者の洗濯や乾燥、アイロンがけ。
- 廃棄:ゴミとして焼却される際の排出。
このように、ファッション産業は気候変動にも大きな影響を与えており、このままの状況を続けることはできないという危機感が、サステナブルな取り組みを加速させる大きな要因となっています。
ファッション業界における人権・労働問題
サステナブルファッションが注目される理由は、環境問題だけではありません。私たちの着ている服が、誰かの犠牲の上に成り立っているかもしれないという、社会的な問題への意識の高まりも非常に重要です。
劣悪な労働環境
安価なファストファッションを実現するための徹底したコスト削減は、多くの場合、生産を担う発展途上国の労働者にそのしわ寄せが及びます。
この問題が世界的に大きくクローズアップされるきっかけとなったのが、2013年にバングラデシュの首都ダッカ近郊で起きた「ラナ・プラザ崩落事故」です。複数の縫製工場が入った商業ビルが倒壊し、1,100人以上の労働者が亡くなり、2,500人以上が負傷するという大惨事でした。このビルには、亀裂が見つかり危険性が指摘されていたにもかかわらず、多くの労働者が働かされ続けていたのです。
この悲劇は、私たちが着ている服の裏側にある、以下のような劣悪な労働環境の実態を浮き彫りにしました。
- 危険な建物や設備:耐震基準を満たしていない、消火設備が不十分など、安全が確保されていない環境での作業。
- 非衛生的な環境:換気が悪く、粉塵や化学物質が蔓延する中での長時間労働。
- 過酷な長時間労働:納期のプレッシャーから、法定時間をはるかに超える残業が常態化。
ラナ・プラザの事故をきっかけに、消費者の間で「#WhoMadeMyClothes(私の服は誰が作ったの?)」というハッシュタグを使った運動が広まり、企業に対してサプライチェーン(製品が消費者に届くまでの全工程)の透明性を求める声が強まりました。
児童労働や不当な低賃金
安さを追求するあまり、さらに深刻な人権侵害も起きています。
- 児童労働:本来であれば学校に通うべき年齢の子どもたちが、家計を助けるために低賃金で働かされている問題です。特に、原料となるコットンの栽培や、複雑なサプライチェーンの末端で行われる手作業などで、児童労働が依然として存在すると指摘されています。
- 不当な低賃金:多くの労働者は、最低限の生活を維持するために必要な賃金(リビングウェイジ)をはるかに下回る、不当に安い賃金で働かされています。これにより、貧困から抜け出すことができず、子どもを働かせざるを得ないという悪循環も生まれています。
- 労働者の権利の抑圧:労働組合を結成する権利や、団体交渉を行う権利が認められず、労働者が自らの待遇改善を求めて声を上げることが困難な状況も多く見られます。
これらの環境問題や人権・労働問題が、インターネットやSNSを通じて世界中に広く知られるようになったことで、多くの消費者が「安ければ良い」「流行っていれば良い」という価値観だけでは服を選べなくなってきました。自分の消費行動が、地球環境や誰かの人権にどのような影響を与えるのかを考えるようになり、その結果として、より透明性が高く、環境や社会に配慮したサステナブルなファッションを求める声が世界的な潮流となったのです。
サステナブルファッションに関連する重要なキーワード
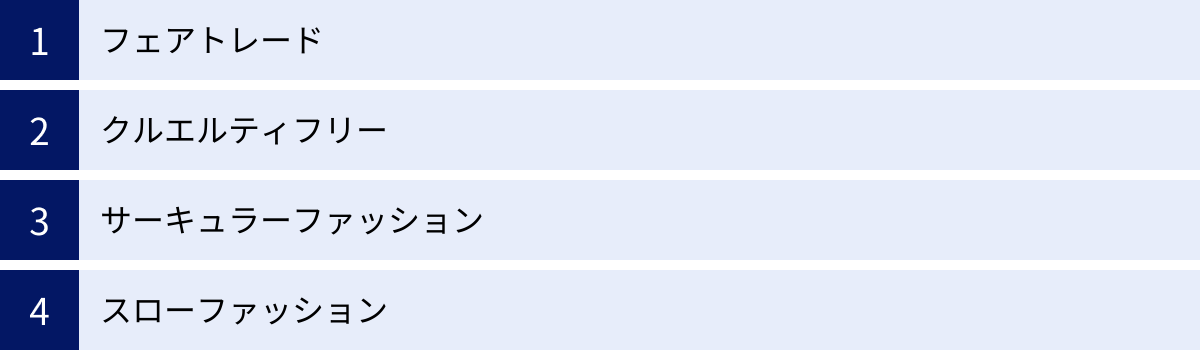
サステナブルファッションの世界をより深く理解するためには、いくつかの重要なキーワードを知っておく必要があります。ここでは、特によく使われる4つの概念「フェアトレード」「クルエルティフリー」「サーキュラーファッション」「スローファッション」について、それぞれ詳しく解説します。
フェアトレード
フェアトレード(Fair Trade)とは、直訳すると「公正な貿易」を意味します。これは、発展途上国の小規模な生産者や労働者が作った農産物や製品を、適正な価格で継続的に買い取ることにより、彼らの生活改善と自立を支援する貿易の仕組みです。
- 背景:グローバルな市場経済では、発展途上国の生産者は価格決定力が弱く、国際市場の価格変動や仲介業者による買い叩きなどによって、不安定で低い収入しか得られないという問題があります。フェアトレードは、こうしたアンフェアな構造を是正するために生まれました。
- 仕組み:フェアトレードには、以下のような基準が設けられています。
- 最低価格の保証:市場価格がどんなに下落しても、生産者の持続可能な生活を支えるために最低限の価格を保証します。
- プレミアム(奨励金)の支払い:生産者が地域社会の発展(学校や病院の建設、インフラ整備など)のために使える奨励金を、買取価格に上乗せして支払います。
- 長期的な取引:安定した生産計画が立てられるよう、長期的なパートナーシップを築きます。
- 安全な労働環境と児童労働・強制労働の禁止:労働者の人権が守られることを保証します。
- 環境への配慮:農薬の使用削減や有機農法の推進など、環境に優しい生産方法を奨励します。
ファッションの分野では、「フェアトレード認証コットン」を使用したTシャツやシャツなどが代表的です。私たちがフェアトレード製品を選ぶという行為は、単なる買い物に留まらず、遠い国の生産者の生活を直接的に支え、より公平で持続可能な社会を築くための一票を投じることに繋がります。国際フェアトレード認証ラベルなどが付いた製品は、これらの基準を満たしていることの証となります。
クルエルティフリー
クルエルティフリー(Cruelty-Free)とは、「残虐性のない」という意味の言葉です。これは、製品やその成分が、開発から製造、加工に至るどの段階においても、動物を傷つけたり殺したりするような実験や行為を一切行っていないことを示します。
もともとは化粧品業界で、製品の安全性を確認するためにウサギやマウスなどを使って行われる動物実験に反対する動きから広まりましたが、現在ではファッション業界でも非常に重要な概念となっています。
ファッションにおけるクルエルティフリーの主なポイントは以下の通りです。
- リアルファー(毛皮)の不使用:キツネ、ミンク、ウサギなどを毛皮のためだけに飼育し、殺処分することに反対する考え方。多くの高級ブランドもリアルファーの使用廃止を宣言しています。
- アンゴラやダウンなどへの配慮:アンゴラウサギの毛を生きたままむしり取る、水鳥の胸の羽毛を生きたままむしり取る(ライブハンドプラッキング)といった、動物に多大な苦痛を与える方法で採取された素材を使用しないこと。
- ウールへの配慮:羊への寄生虫を防ぐために、麻酔なしで子羊の臀部の皮膚と肉を切り取る「ミュールシング」という行為を行わない、「ノンミュールシングウール」を選択すること。
- レザーの代替:動物の皮を使用せず、植物由来の素材(パイナップルやキノコなど)や合成素材から作られる「ヴィーガンレザー」への注目。
クルエルティフリーは、人間だけでなく、地球上に共に生きる動物たちの命や福祉(アニマルウェルフェア)も尊重しようという倫理的な考え方に基づいています。動物実験を行っていないことを示す「リーピングバニー」マークや、動物由来の成分を一切含まないことを示す「ヴィーガン認証」マークなどが、製品選びの参考になります。
サーキュラーファッション(循環型ファッション)
サーキュラーファッション(Circular Fashion)とは、従来の「作って、使って、捨てる」という一方通行の直線型(リニア)経済から脱却し、資源を廃棄することなく、可能な限り長く、高い価値を保ったまま循環させ続けることを目指すファッションのあり方です。これは、大量生産・大量廃棄問題に対する最も根本的な解決策の一つとして期待されています。
サーキュラーファッションの概念は、主に以下の3つの原則に基づいています。(エレン・マッカーサー財団の定義より)
- 廃棄物と汚染を出さないデザイン(Design out waste and pollution):
- 製品を設計する段階から、廃棄物が出ないように工夫すること。例えば、リサイクルしやすいように単一素材で作ったり、解体しやすい構造にしたりします。
- 有害な化学物質を使わず、環境に安全な素材を選ぶことも含まれます。
- 製品と素材を使い続ける(Keep products and materials in use):
- 一度作られた服を、できるだけ長く使い続けるための仕組みを作ること。これには、修理(リペア)、再販(リセール)、レンタル、サブスクリプションなどが含まれます。
- 古着を回収し、デザインを変えて新たな価値を持つ製品に作り替える「アップサイクル」も重要な取り組みです。
- 最終的に服として使えなくなったものは、繊維レベルまで分解して新しい糸や生地に再生する「リサイクル」を行います。
- 自然システムを再生する(Regenerate natural systems):
- 化学肥料に頼らず、土壌の健康を回復・維持するような農法(リジェネラティブ農業)で栽培されたコットンやリネンなど、自然環境を再生することに繋がる素材を使用すること。
サーキュラーファッションは、ゴミを「終わり」と捉えず、「次の始まり」の資源として捉え直す、経済システム全体の変革を目指す壮大なビジョンです。企業の製品回収プログラムや、レンタルサービスの利用は、私たち消費者がサーキュラーファッションに参加する具体的な方法と言えます。
スローファッション
スローファッション(Slow Fashion)は、その名の通り、ファストファッションの対極にある考え方です。目まぐるしく変わるトレンドを追いかけるのではなく、一着の服をじっくりと選び、長く大切に着続けることを価値とするライフスタイルやムーブメントを指します。
スローファッションが重視する価値観は以下の通りです。
- 品質と耐久性:安価ですぐにダメになる服ではなく、質の良い素材を使い、丁寧な縫製で作られた、丈夫で長持ちする服を選びます。
- タイムレスなデザイン:一過性の流行に左右されない、普遍的で長く愛用できるクラシックなデザインを好みます。
- 作り手の物語:大量生産品ではなく、地域の職人による手仕事や、作り手の顔が見える小規模なブランドの製品に価値を見出します。生産背景にあるストーリーを大切にします。
- 意識的な消費:「安いから」「流行っているから」という理由で衝動買いするのではなく、購入前に「これは本当に自分に必要か?」「何年も着続けられるか?」とじっくり考えます。自分のワードローブを量より質で満たしていく姿勢です。
スローファッションは、単に服を買うペースを落とすことだけを意味するのではありません。服との関係性そのものを見直し、一つひとつの持ち物を慈しみ、丁寧に暮らすという、より豊かで哲学的なアプローチです。自分のクローゼットの中にある服を修理したり、リメイクしたりして楽しむことも、スローファッションの実践と言えるでしょう。
サステナブルファッションの具体的な取り組みと基準
サステナブルファッションという大きな概念を、企業はどのように実践しているのでしょうか。また、私たち消費者は、何を手がかりにサステナブルな製品を選べばよいのでしょうか。ここでは、具体的な取り組みと、その信頼性を判断するための基準について解説します。
環境に配慮した素材を選ぶ
サステナブルファッションの最も分かりやすい入り口が「素材選び」です。従来の素材に比べて、環境への負荷が低いとされる様々な選択肢が登場しています。
| 素材カテゴリー | 具体例 | 特徴・メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| オーガニック素材 | オーガニックコットン、オーガニックリネン、オーガニックウール | 3年以上、農薬や化学肥料を使わない農地で栽培・飼育。土壌汚染や水質汚染のリスクが低く、生産者の健康も守られる。 | 従来の農法に比べて収穫量が少なく、価格が高くなる傾向がある。 |
| リサイクル素材 | リサイクルポリエステル、リサイクルナイロン、リサイクルコットン | ペットボトルや漁網、工場の裁断くず、古着などを再利用。新たな石油資源の使用を抑え、廃棄物を削減できる。 | リサイクルの過程でエネルギーを消費する。混紡素材はリサイクルが難しい場合がある。 |
| 再生繊維 | テンセル™、リヨセル、モダール、キュプラ | 木材パルプ(ユーカリなど)や、コットンの種の周りのうぶ毛(コットンリンター)を特殊な溶剤で溶かして再生した繊維。生分解性があり、製造工程で溶剤を回収・再利用するため環境負荷が低い。 | 木材の調達元が適切に管理された森林(FSC認証など)であるかどうかが重要。 |
| 植物由来の代替素材 | 和紙、ヘンプ(麻)、カポック、コルク、パイナップルレザー、マッシュルームレザー | 成長が早い植物や、従来は廃棄されていた農業副産物を利用。動物由来の素材(レザーなど)の代替となる。 | 新しい素材が多く、耐久性や供給の安定性がまだ発展途上のものもある。 |
これらの素材を選ぶことは、環境負荷の低減に直接貢献する重要なアクションです。製品のタグや説明文で、どのような素材が使われているかを確認する習慣をつけましょう。特に、リサイクル素材や再生繊維は、技術革新によってファッションの可能性を広げながら、環境問題の解決にも繋がる注目の分野です。
3R(リデュース・リユース・リサイクル)を推進する
3Rは、環境配慮の基本原則であり、サステナブルファッションにおいても中心的な役割を果たします。
- リデュース(Reduce):廃棄物の発生を抑制する
- これが最も重要で、効果的な取り組みです。 企業側は、需要予測の精度を上げて過剰な生産をなくしたり、受注生産モデルを導入したりすることで、売れ残りによる廃棄を根本から減らす努力が求められます。
- また、消費者側は、衝動買いを控えて「本当に必要な服だけを買う」ことが最大のリデュースに繋がります。
- リユース(Reuse):繰り返し使う
- 一度役目を終えた製品を、ゴミにせずに再利用することです。
- 企業の取り組み:自社製品を回収してクリーニングや修理を施し、中古品として再販売するプログラム(例:パタゴニアの「Worn Wear」)。
- 新しいビジネスモデル:月額制で服を借りられるレンタルサービスやサブスクリプション。これにより、消費者は多くの服を所有することなく、様々なファッションを楽しめます。
- 個人の取り組み:古着屋やフリマアプリで服を売買することも、リユースの立派な実践です。
- リサイクル(Recycle):資源として再利用する
- リユースできなくなった衣類を、原料に戻して新たな製品に作り替えることです。
- 店頭回収:多くのアパレルブランドが店舗に回収ボックスを設置し、自社・他社問わず不要になった衣類を回収しています。
- リサイクルの種類:
- マテリアルリサイクル:回収した服を反毛(わた)に戻し、軍手や断熱材、車の内装材などに加工します。
- ケミカルリサイクル:化学的に繊維を分子レベルまで分解し、再び新しい糸やポリエステル原料として再生する高度な技術です。これにより、品質を落とさずに何度も循環させることが可能になります。
- 回収された衣類の一部は、状態が良いものは選別されて海外の難民キャンプなどに寄付されることもあります。
3Rは、「リデュース → リユース → リサイクル」の優先順位で考えることが重要です。まずはゴミを生まない工夫をし、次に再利用を考え、最後の手段としてリサイクルするという意識を持つことが、循環型社会の実現に繋がります。
アニマルウェルフェア(動物福祉)を尊重する
アニマルウェルフェアとは、動物が心身ともに健康で、幸福であり、環境とも調和している状態を目指す考え方です。ファッションのために、動物が不必要な苦痛を受けたり、劣悪な環境で飼育されたりすることがないように配慮することも、サステナビリティの重要な側面です。
- 脱・リアルファー:多くのラグジュアリーブランドがリアルファーの使用廃止を宣言し、高品質なエコファー(フェイクファー)への移行が進んでいます。
- 責任あるダウン:「Responsible Down Standard (RDS)」などの認証は、生きた鳥からの羽毛採取(ライブハンドプラッキング)や強制給餌などを行わず、人道的に飼育された水鳥から採取されたダウンであることを保証します。
- ノンミュールシングウール:羊への寄生バエのウジの発生を防ぐために、麻酔なしで子羊の臀部の皮膚を切り取る「ミュールシング」は、動物愛護の観点から問題視されています。これを行わない「ノンミュールシングウール」を選ぶブランドが増えています。
- ヴィーガンレザー:動物の皮を使わず、ポリウレタンなどの合成素材や、パイナップルの葉、キノコ、リンゴの皮など、植物由来の原料から作られる代替レザーです。技術の進歩により、本革と見紛うほどの質感を持つものも登場しています。
これらの取り組みは、クルエルティフリーの考え方とも直結しており、倫理的な観点からブランドや製品を選ぶ際の重要な判断基準となります。
国際的な認証ラベルを確認する
企業のウェブサイトや広告には「サステナブル」「エコ」といった言葉が溢れていますが、その主張が本当に信頼できるものか、消費者が見極めるのは簡単ではありません。そこで役立つのが、第三者機関による客観的な審査を経て与えられる「国際認証ラベル」です。これらは、企業が特定の環境・社会基準を満たしていることの信頼性の高い証となります。
| 認証ラベル名 | 対象分野 | 主な基準の概要 |
|---|---|---|
| GOTS (Global Organic Textile Standard) | オーガニックテキスタイル | 原料の70%以上(ラベルグレードによる)がオーガニック認証を受けた繊維であること。製造の全工程で、環境負荷や毒性に関する厳しい基準、労働者の人権に関する社会的な基準をクリアしている必要がある。オーガニック製品の信頼性を測る世界的な基準。 |
| 国際フェアトレード認証ラベル | コットン、その他農産物 | 発展途上国の生産者に対し、公正な価格での買い取り、長期的な取引、児童労働・強制労働の禁止、安全な労働環境などを保証する。生産者の自立と生活向上を支援する。 |
| FSC® (Forest Stewardship Council®) | 森林製品(再生セルロース繊維、紙タグなど) | 環境保全の点から見て適切で、社会的な利益にかない、経済的にも継続可能な、責任ある管理をされた森林からの木材製品であることを証明する。違法伐採や森林破壊を防ぐ。 |
| bluesign® (ブルーサイン) | 繊維製品全般 | 「繊維業界の最も厳しい基準」とも言われる。原料から最終製品までの全製造工程において、有害な化学物質を排除し、水や大気への排出を管理。労働者、消費者、環境にとって安全な製品であることを保証する。 |
| Responsible Down Standard (RDS) | ダウン・フェザー製品 | ダウンが、強制給餌やライブハンドプラッキングといった非人道的な扱いを受けていない水鳥から採取されたものであることを保証する、アニマルウェルフェアに関する認証。 |
| The Global Recycled Standard (GRS) | リサイクル製品 | 製品に含まれるリサイクル素材の含有率が正しいことを検証するだけでなく、その製造過程において、環境配慮(水・エネルギー使用、化学物質管理など)や、労働者の権利保護といった社会的な基準も満たしていることを証明する。 |
これらの認証ラベルは、専門的な知識がなくても、製品がサステナブルな背景を持っているかどうかを判断できる便利なツールです。ただし、認証の取得や維持にはコストがかかるため、小規模なブランドでは取得が難しい場合もあります。ラベルの有無だけでなく、ブランドが発信する情報や姿勢を総合的に見て判断することが大切です。
個人でできるサステナブルファッションへの取り組み8選
サステナブルファッションは、企業だけの取り組みではありません。私たち消費者一人ひとりの日々の選択や行動が、業界全体をより良い方向へ導く大きな力となります。ここでは、誰でも今日から始められる8つの具体的なアクションを紹介します。
① 本当に必要な服だけを買う
最も簡単で、最も効果的なアクションが「買いすぎないこと」です。これは、大量生産・大量廃棄のサイクルを断ち切るための最も根本的な解決策(リデュース)です。
- 買う前に一度立ち止まる:セールや新作に心が動いても、すぐにレジに持っていく前に「これは本当に必要か?」「手持ちの服で似たものはないか?」「最低でも3通りの着回しができるか?」「30回以上着るだろうか?」といった質問を自分に問いかけてみましょう。
- クローゼットの中身を把握する:定期的に自分の持っている服を確認し、写真に撮ったりリストアップしたりしておくと、似たような服を買ってしまう失敗を防げます。
- 「1 in, 1 out」ルールを試す:もし新しい服を1着買ったら、代わりにクローゼットから1着手放すというルールを設けるのも、服が増えすぎるのを防ぐのに効果的です。
衝動買いを減らし、吟味して選んだ一着を迎えることは、無駄な消費と廃棄を減らすだけでなく、自分のワードローブへの愛着を深めることにも繋がります。
② 一つの服を長く大切に着る
スローファッションの考え方を取り入れ、「安くてたくさん」から「良質で少なく」へと価値観をシフトしてみましょう。
- 品質を見極める:購入する際には、デザインだけでなく、生地の質感や縫製の丁寧さもチェックしましょう。丈夫で仕立ての良い服は、価格が少し高くても結果的に長く着ることができ、コストパフォーマンスも高くなります。
- トレンドに左右されない:一時的な流行を追うのではなく、何年経っても着られるベーシックなデザインや、自分が本当に好きだと感じる普遍的なスタイルのアイテムを選ぶことが、長く愛用する秘訣です。
- 自分の体に合ったサイズを選ぶ:無理なサイズや似合わないデザインの服は、結局着なくなってしまいます。試着をしっかりして、自分の体型にフィットし、着ていて心地よいと感じる服を選びましょう。
一つの服を長く着続けることは、新たな服の生産に必要な資源やエネルギーを節約し、廃棄物を減らす直接的な環境貢献になります。
③ 正しい方法でお手入れして服を長持ちさせる
お気に入りの服も、お手入れの方法を間違えるとすぐに傷んでしまいます。正しいケアは、服の寿命を格段に延ばします。
- 洗濯表示を必ず確認する:服の内側についているタグには、洗い方、干し方、アイロンのかけ方など、その服に最適なケア方法が記されています。洗濯機で洗えるか、手洗いが必要か、乾燥機は使えるかなど、洗濯前に必ずチェックしましょう。
- 素材に合わせた洗い方:デリケートなニットや装飾のある服は、洗濯ネットに入れたり、手洗いしたりすることで型崩れや傷みを防げます。色落ちしやすい服は、他のものと分けて洗いましょう。
- 洗濯の頻度を見直す:毎回着るたびに洗濯する必要のないアウターやジーンズなどは、洗濯の頻度を減らすだけでも生地へのダメージを抑え、水や電力の節約になります。
- 正しい干し方と保管:ニットはハンガーに吊るすと伸びてしまうので、平干しするのが基本です。直射日光は色褪せの原因になるので、風通しの良い日陰で干しましょう。保管する際は、防虫剤を使ったり、湿気を避けたりして、衣類が傷まない環境を整えることが大切です。
丁寧なケアは、服への愛情表現でもあります。一手間かけることで、大切な一着との付き合いはもっと長くなります。
④ 自分で修理(リペア)やリメイクを楽しむ
ボタンが取れた、裾が少しほつれた。そんな小さなダメージで、すぐに服を諦めていませんか?簡単な修理(リペア)は、サステナブルな習慣の第一歩です。
- 簡単な裁縫に挑戦:ボタン付けやほつれ縫いは、基本的な裁縫道具があれば誰でもできます。YouTubeなどで検索すれば、分かりやすい動画がたくさん見つかります。
- ダーニングを楽しむ:セーターの穴あきなどを、あえてカラフルな糸で装飾的に補修する「ダーニング」は、修理をクリエイティブな表現に変える楽しい手法です。
- リメイクで新たな命を:サイズが合わなくなったり、デザインに飽きてしまったりした服は、リメイクで生まれ変わらせましょう。着なくなったTシャツをエコバッグに、古いジーンズをクッションカバーやポーチに作り変えるなど、アイデアは無限大です。
自分の手で服を直し、作り変えることは、モノを大切にする心を育み、創造性を刺激する豊かな時間となります。
⑤ 古着やリユース品をファッションに取り入れる
新しい服が必要になったとき、選択肢は新品だけではありません。古着やリユース品は、環境に優しく、経済的で、個性的なファッションを楽しむための素晴らしい選択肢です。
- 古着屋やスリフトショップを巡る:一点ものの宝探しのような感覚で、自分だけの特別な一着を見つける楽しみがあります。
- オンラインのフリマアプリを活用する:スマートフォン一つで、手軽に個人間の服の売買ができます。探しているアイテムが、思いがけない価格で見つかることもあります。
- リユースのメリット:新品の服を生産する際に必要な水、エネルギー、CO2排出をゼロにできる、最も直接的な環境貢献の一つです。また、他の人とは被らない、ユニークなスタイルを表現できます。
⑥ 服のレンタルやサブスクリプションを利用する
「所有」から「共有(シェア)」へ。この新しい考え方は、クローゼットをすっきりと保ちながら、様々なファッションを楽しむことを可能にします。
- 特別な日のためのレンタル:結婚式やパーティーなど、一度しか着る機会のないドレスやスーツは、レンタルサービスを利用するのが賢い選択です。購入するよりも安価で、保管場所に困ることもありません。
- 日常着のサブスクリプション:月額定額制で、プロのスタイリストが選んだ服が毎月届くサービスです。色々なブランドやスタイルの服を試すことができ、気に入らなければ返却するだけ。手持ちの服を増やすことなく、ファッションの幅を広げられます。
必要な時に必要な服だけを利用する」というスタイルは、無駄な消費を抑える、非常にスマートなサステナブルアクションです。
⑦ 着なくなった服はリサイクルや寄付をする
どうしても手放すことになった服は、ゴミとして捨てる前に、次の活躍の場を探してあげましょう。
- 店頭の回収ボックスを利用する:ユニクロやH&Mなど、多くのブランドが自社・他社問わず衣類を回収するボックスを店舗に設置しています。回収された服は、リユースやリサイクルに回されます。
- 自治体の資源回収に出す:お住まいの自治体のルールに従って、古布として資源回収に出すことができます。
- 寄付をする:NPOやNGOを通じて、国内外で衣類を必要としている人々に届けることができます。ただし、寄付できるのはまだ十分に着用できる状態のものに限られることが多いので、事前に団体の条件を確認しましょう。
- フリマアプリやリサイクルショップで売る:まだ価値のある服は、次の持ち主を見つけることでリユースに繋がります。
手放す時まで責任を持つことが、サステナブルなファッションサイクルの最後の重要なステップです。
⑧ サステナブルに取り組むブランドを選んで応援する
私たち消費者の「買う」という行為は、その企業やブランドを支持する「投票」と同じ意味を持ちます。
- ブランドの姿勢を調べる:購入を検討しているブランドの公式ウェブサイトには、サステナビリティに関するページが設けられていることが多いです。どのような素材を使っているか、工場の労働環境にどう配慮しているか、どんな社会貢献活動をしているかなどをチェックしてみましょう。
- 認証ラベルを参考にする:前述したGOTSやフェアトレード認証などのラベルは、そのブランドの取り組みが客観的に評価されている証拠であり、信頼できる判断材料になります。
- 小さなブランドを応援する:地域に根差した小規模なブランドや、明確な哲学を持ってものづくりをしているブランドを応援することも、ファッションの多様性を支え、業界全体を豊かにすることに繋がります。
意識的にブランドを選ぶ消費者が増えれば、企業もサステナブルな取り組みをせざるを得なくなります。私たち一人ひとりの選択が、より良いファッションの未来を作る原動力になるのです。
サステナブルファッションに取り組むおすすめブランド10選
ここでは、サステナブルファッションを牽引する、国内外の代表的なブランドを10選紹介します。各ブランドがどのような哲学を持ち、具体的な取り組みを行っているのかを知ることは、あなたのブランド選びの参考になるはずです。
(※各ブランドの情報は、公式サイト等で公開されている内容に基づいています。)
① Patagonia (パタゴニア)
- 概要:アメリカ発のアウトドアウェアブランド。創業当初から環境保護活動に積極的に取り組み、サステナブルファッションの分野では誰もが認めるリーダー的存在です。
- 主な取り組み:
- Worn Wear®:製品を修理(リペア)して長く使うことを奨励するプログラム。修理サービスの提供や、回収した古着を修理・クリーニングして再販しています。
- リサイクル素材の積極利用:ペットボトルから再生したリサイクル・ポリエステルを早くから採用するなど、環境負荷の低い素材開発をリード。
- フェアトレード認証:多くの製品がフェアトレード・サーティファイドの工場で製造されており、労働者の生活向上を支援しています。
- 1% for the Planet:売上の1%を自然環境の保護・回復のために寄付する自主的な税金を課しています。
- 参照:パタゴニア公式サイト
② Stella McCartney (ステラ マッカートニー)
- 概要:イギリス発のラグジュアリーブランド。デザイナー自身の信念に基づき、ブランド設立当初からサステナビリティとアニマルウェルフェアをブランドの核に据えています。
- 主な取り組み:
- ベジタリアンブランド:レザー、ファー、フェザー、スキンを一切使用しないクルエルティフリーを徹底。
- 革新的なサステナブル素材:オーガニックコットンやリサイクル素材はもちろん、キノコの菌糸体から作られた代替レザー「Mylo™」や、ブドウの廃棄物から作られたヴィーガンレザーなど、最先端の素材を積極的に開発・採用。
- 透明性の高いサプライチェーン:素材の調達先や生産背景を公開し、環境・社会への影響を追跡しています。
- 参照:ステラ マッカートニー公式サイト
③ People Tree (ピープルツリー)
- 概要:イギリス発の、フェアトレードを専門とするファッションブランドのパイオニア。日本の代表であるサフィア・ミニー氏によって設立されました。
- 主な取り組み:
- WFTO(世界フェアトレード機関)認証:生産から販売まで、フェアトレードの原則を一貫して守っていることを証明する認証を長年にわたり受け続けています。
- 手仕事と伝統技術の活用:アジアやアフリカ、南米の生産者パートナーと共に、手織り、手刺繍、草木染めといった、環境負荷が少なく、地域の文化を継承する技術を活かした製品作りを行っています。
- オーガニックコットン:GOTS認証を受けたオーガニックコットンを積極的に使用しています。
- 参照:ピープルツリー公式サイト
④ Veja (ヴェジャ)
- 概要:フランス発の、ミニマルなデザインで人気を集めるスニーカーブランド。デザインの裏側にある、徹底した透明性とサステナブルなものづくりが支持されています。
- 主な取り組み:
- 公正な原料調達:ブラジルの生産者から、フェアトレードの原則に基づいてオーガニックコットンやアマゾンの天然ゴムを直接買い付けています。
- アップサイクル素材と代替レザー:ペットボトルをリサイクルした生地や、トウモロコシの廃棄物から作られたヴィーガンレザー「C.W.L.」など、革新的な素材を使用。
- 徹底した透明性:原材料の価格や労働者の賃金など、コスト構造をウェブサイトで公開しています。
- 参照:Veja公式サイト
⑤ Allbirds (オールバーズ)
- 概要:アメリカ・サンフランシスコ発のシューズブランド。「世界で最も快適な靴」を掲げ、自然由来の革新的な素材とシンプルなデザインで急成長しました。
- 主な取り組み:
- 自然由来の革新的素材:ZQ認証を受けたメリノウール、FSC認証を受けたユーカリの木の繊維(テンセル™リヨセル)、サトウキビ由来でカーボンネガティブなEVAフォーム「SweetFoam®」などを開発・使用。
- カーボンフットプリントの表示:全製品のライフサイクルにおけるCO2排出量を計算し、商品に明記。2030年までに排出量をほぼゼロにする目標を掲げています。
- B Corp認証:環境や社会への配慮、透明性などに関する厳しい基準をクリアした企業に与えられる国際的な認証を取得しています。
- 参照:Allbirds公式サイト
⑥ 無印良品
- 概要:日本を代表するライフスタイルブランド。「素材の選択」「工程の点検」「包装の簡略化」という視点を創業以来持ち続け、総合的なサステナビリティを追求しています。
- 主な取り組み:
- オーガニックコットンの推進:長年にわたり、農薬や化学肥料を使わずに栽培されたオーガニックコットン製品の展開を拡大しています。
- ReMUJI:全国の店舗で自社の衣料品を回収し、染め直して再生した服や、リサイクル製品として販売するプログラム。
- 残布の活用:生産工程で出る布の端切れを無駄にせず、小物や衣類の一部に活用しています。
- 参照:株式会社良品計画公式サイト
⑦ UNIQLO (ユニクロ)
- 概要:世界的なSPA(製造小売業)ブランド。グローバル企業としての責任を果たし、ビジネスを通じて社会をより良くすることを目指しています。
- 主な取り組み:
- RE.UNIQLO:顧客から不要になったユニクロの服を回収し、リユース(難民キャンプなどへの衣料支援)とリサイクル(新しい服の素材や燃料・防音材への再資源化)を推進。
- ブルーサイクルジーンズ:ジーンズの仕上げ工程で、最新の機器とナノバブル技術により、水の使用量を最大99%削減。
- サプライチェーンの透明性:主要な素材工場や縫製工場のリストを公開し、労働環境の監査を定期的に実施しています。
- 参照:株式会社ファーストリテイリング公式サイト
⑧ H&M (エイチ・アンド・エム)
- 概要:スウェーデン発の世界最大級のファストファッションブランド。その規模を活かし、サステナビリティを主流にすることを目指し、様々な取り組みを行っています。
- 主な取り組み:
- 古着回収プログラム:2013年から世界中の店舗でブランドを問わず衣料品を回収。リユース、リウェア、リサイクルに活用しています。
- サステナブルな素材への転換:オーガニックコットンやリサイクル素材などを使用した「コンシャス・コレクション」を展開。2030年までに全ての素材をリサイクルまたはその他サステナブルに調達されたものに切り替えるという高い目標を掲げています。
- イノベーションへの投資:新しいリサイクル技術やサステナブル素材を開発する企業を支援する「グローバル・チェンジ・アワード」を主催。
- 参照:H&M公式サイト
⑨ KAPOK KNOT (カポックノット)
- 概要:「カポック」という木の実由来の素材を使ったアウターウェアを中心に展開する、日本発のブランドです。
- 主な取り組み:
- アニマルフリー:ダウンの5分の1の軽さで、暖かさはダウン以上とされる植物由来の素材「カポック」を使用。動物の犠牲を伴わない製品作りを徹底しています。
- 環境負荷の低減:カポックは栽培に農薬や大量の水を必要としないため、環境負荷が低い素材です。
- 廃棄削減:受注生産モデルを取り入れるなど、過剰在庫による廃棄を減らす努力をしています。
- 参照:KAPOK KNOT公式サイト
⑩ Enter the E (エンター・ザ・イー)
- 概要:特定のブランドではなく、国内外のサステナブル・エシカルなファッションブランドを厳選して取り扱う、日本のセレクトショップです。
- 主な取り組み:
- 独自の厳格な基準:「生産背景の透明性」「環境や社会への貢献」「サステナブルな素材の使用」など、独自の基準をクリアしたブランドのみをセレクト。
- ストーリーの伝達:製品のデザインだけでなく、その背景にあるブランドの想いやストーリー、生産者の物語を丁寧に伝えることで、消費者の共感を呼び、価値の理解を深めています。
- 多様な選択肢の提供:様々なテイストや価格帯のサステナブルブランドを紹介することで、消費者が自分のスタイルに合った選択をする手助けをしています。
- 参照:Enter the E公式サイト
まとめ
この記事では、「サステナブルファッション」とは何か、その背景にある問題、そして企業や私たち個人ができる具体的な取り組みについて、多角的に解説してきました。
サステナブルファッションとは、単なる一過性のトレンドや、環境に配慮した素材を使った服という限定的なものではありません。それは、衣服の生産から廃棄に至る全行程で、地球環境と社会に対する責任を果たし、未来の世代も豊かに暮らし続けられるようなファッション産業のあり方を目指す、包括的で本質的なムーブメントです。
その背景には、ファストファッションが加速させた「大量生産・大量廃棄」、生産過程における「水質汚染・CO2排出」、そして生産現場での「劣悪な労働環境・人権侵害」といった、無視できない深刻な問題があります。
これらの課題に対して、私たちは決して無力ではありません。
「本当に必要なものだけを買い、一着を長く大切に着る」
これは、誰にでも今日から始められる、最もパワフルなアクションです。さらに、正しいお手入れで服の寿命を延ばし、修理やリメイクを楽しみ、着なくなった服はリサイクルや寄付に回す。そして、買い物をするときには、その製品の裏側にあるストーリーに思いを馳せ、環境や社会に配慮するブランドを意識的に選んで応援すること。
こうした一つひとつの小さな選択が、積み重なることで大きな力となり、企業を、そしてファッション業界全体をより良い方向へと動かしていく原動力となります。
「服を選ぶ」という日常の行為が、地球の未来を守り、世界中の誰かの暮らしを支えることに繋がる。サステナブルファッションは、私たちにそんな新しい価値観と、より豊かで意味のあるファッションの楽しみ方を教えてくれます。まずは、あなたのクローゼットにある一着を、いつもより少しだけ大切に扱うことから始めてみませんか。