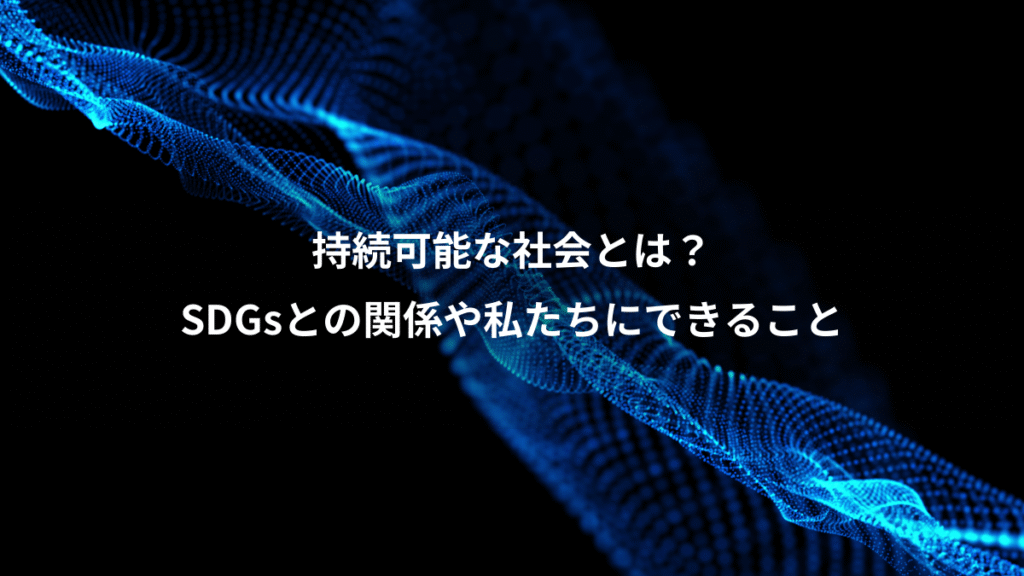現代社会において、「持続可能な社会」や「サステナビリティ」という言葉を耳にする機会が急速に増えています。地球環境問題の深刻化や社会的な格差の拡大など、私たちが直面する課題は複雑化し、これまでの社会経済システムのあり方が問われています。
この記事では、「持続可能な社会」とは具体的にどのような社会を指すのか、その基本的な概念から、なぜ今それが世界的に求められているのかという背景、そして私たちの生活と密接に関わるSDGsとの関係性までを、専門的な視点を交えながら分かりやすく解説します。
さらに、世界や日本、企業がどのような取り組みを進めているのかを概観した上で、私たち一人ひとりが日々の暮らしの中で実践できる具体的なアクションを10個厳選して紹介します。この記事を通じて、持続可能な社会の実現に向けた理解を深め、自分にできることを見つける一助となれば幸いです。
目次
持続可能な社会とは
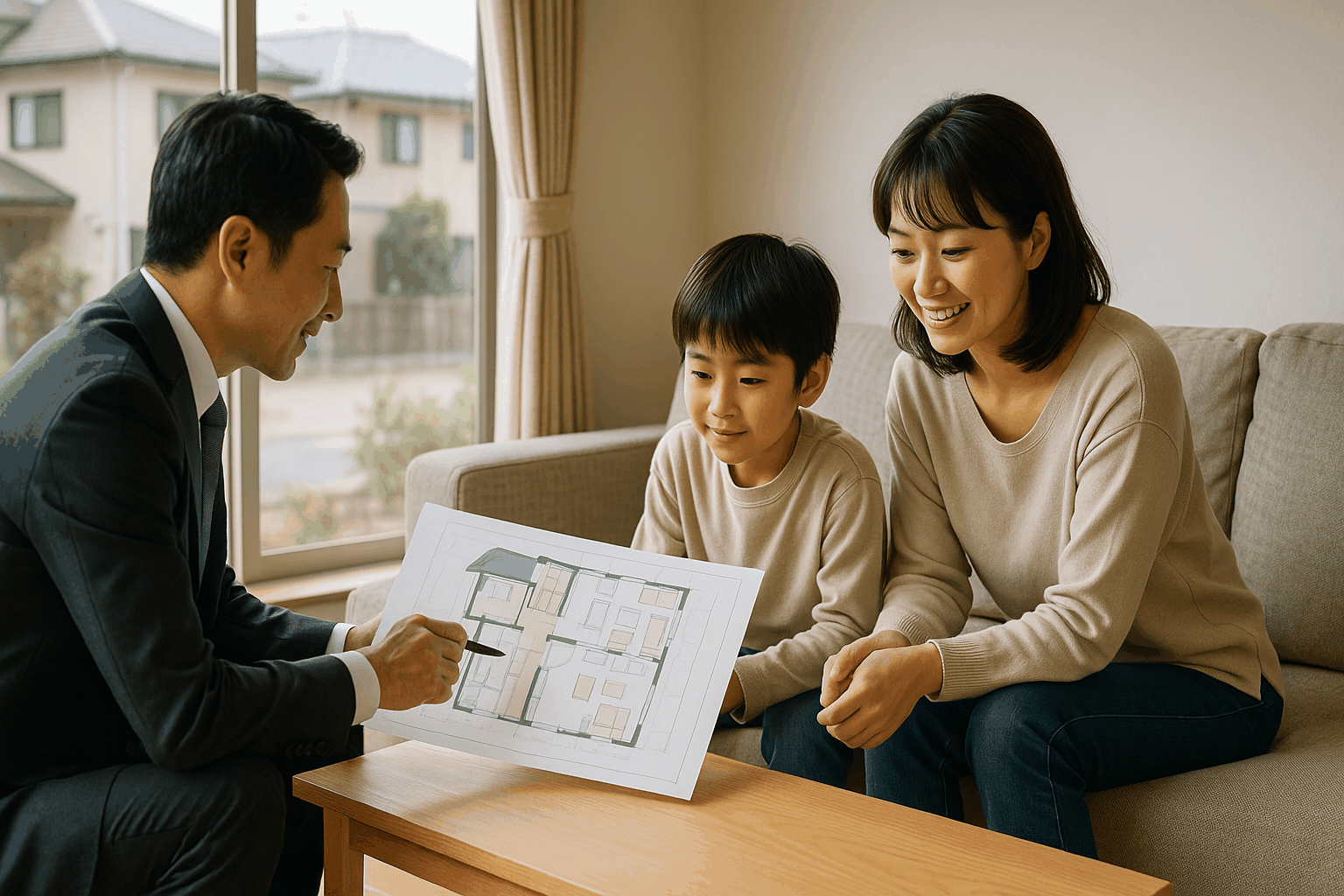
「持続可能な社会」という言葉は、未来を見据えた社会のあり方を示す重要な概念です。しかし、その意味を正確に理解している人はまだ多くないかもしれません。この章では、持続可能な社会の基本的な定義と、その根幹をなす3つの要素について詳しく解説します。
環境・社会・経済のバランスが取れた社会
持続可能な社会とは、端的に言えば「環境の保全」「社会の公正さ」「経済の発展」という3つの要素が調和し、将来の世代が必要とするものを損なうことなく、現代の私たちのニーズを満たすことができる社会のことです。この考え方は、特定の分野だけでなく、私たちの生活のあらゆる側面に関わる包括的なビジョンを示しています。
この概念が国際的に広く認知されるきっかけとなったのが、1987年に国連の「環境と開発に関する世界委員会」が公表した報告書『Our Common Future』(ブルントラント報告書)です。この中で、「持続可能な開発(Sustainable Development)」が「将来の世代の欲求を満たしうる能力を損なうことなしに、現在の世代の欲求を満たすような開発」と定義されました。この定義が、今日の「持続可能な社会」を考える上での世界共通の基盤となっています。
この定義を理解するためには、以下の3つの柱(スリーピラーズ)について考えることが不可欠です。
| 柱(ピラー) | 内容 | 具体的な要素 |
|---|---|---|
| 環境(Environment) | 地球環境と自然資源を保全し、将来の世代に引き継ぐこと。 | 気候変動対策、生物多様性の保全、資源の循環利用、再生可能エネルギーの活用、大気・水質汚染の防止 |
| 社会(Social) | すべての人々の人権が尊重され、健康で文化的な生活を送れる公正な社会を築くこと。 | 貧困の撲滅、飢餓の解消、質の高い教育、ジェンダー平等、健康と福祉の増進、平和と公正 |
| 経済(Economic) | 環境や社会に配慮しながら、安定した経済活動を継続し、人々の生活の質を向上させること。 | 安定した経済成長、働きがいのある人間らしい雇用の創出、イノベーション、循環型経済(サーキュラーエコノミー)への移行 |
1. 環境の持続可能性
環境の持続可能性は、地球という私たち人類の生存基盤を守ることを意味します。地球の資源は無限ではありません。化石燃料や鉱物資源、さらには清浄な水や空気でさえも、無計画に使い続ければいずれ枯渇したり、劣化したりします。また、経済活動に伴う温室効果ガスの排出は地球温暖化を引き起こし、異常気象や生態系の破壊といった深刻な問題をもたらしています。
環境の持続可能性を追求するとは、地球の環境容量(地球が人間の活動による負荷を吸収・浄化できる能力)の範囲内で活動し、自然資本を次の世代に確実に引き継いでいくことです。具体的には、再生可能エネルギーへの転換、省エネルギーの徹底、廃棄物の削減とリサイクル(3R)の推進、森林や海洋などの生態系保全といった取り組みが求められます。
2. 社会の持続可能性
社会の持続可能性は、すべての人が人間としての尊厳を保ち、安心して暮らせる社会の実現を目指します。世界には、今なお貧困や飢餓に苦しむ人々が数多く存在します。また、性別、人種、出身地、障がいの有無などによって教育や雇用の機会が奪われるといった不平等も根強く残っています。
このような格差や不公正は、人々の幸福を損なうだけでなく、社会全体の不安定化を招く要因にもなり得ます。社会の持続可能性を追求するとは、基本的人権の尊重を土台とし、貧困や格差の是正、質の高い教育や医療へのアクセスの確保、ジェンダー平等の実現などを通じて、誰一人取り残さない包摂的な社会を構築することです。
3. 経済の持続可能性
経済の持続可能性は、短期的な利益追求に偏るのではなく、長期的な視点で安定した成長を目指すことを意味します。これまでの経済モデルは、資源を大量に採掘し、製品を大量に生産・消費し、そして大量に廃棄するという「線形経済(リニアエコノミー)」が主流でした。しかし、このモデルは資源の枯渇と環境破壊を加速させるものであり、持続可能ではありません。
経済の持続可能性を追求するとは、環境への負荷を最小限に抑え、社会的な公正さに配慮しながら経済活動を行うことです。具体的には、製品の修理や再利用、リサイクルを前提とした「循環型経済(サーキュラーエコノミー)」への移行や、労働者の権利を守り、働きがいのある雇用を創出すること、そして技術革新(イノベーション)を通じて新たな価値を創造していくことなどが挙げられます。
重要なのは、これら3つの柱は独立しているのではなく、相互に深く関連し合っているという点です。例えば、環境破壊を顧みない経済成長は、長期的には自然災害の増加や資源価格の高騰を招き、経済活動そのものを脅かします。また、貧困や格差が蔓延する社会では、人々は目先の生活のために森林伐採や密猟といった持続可能でない行動を選ばざるを得ない状況に追い込まれることもあります。逆に、環境に配慮した技術への投資は、新たな産業や雇用を生み出し、経済成長に貢献する可能性があります。
このように、持続可能な社会とは、環境・社会・経済のいずれか一つを犠牲にするのではなく、これら三者のバランスを取りながら、統合的に発展させていく社会の姿なのです。それは、私たち現世代の豊かさだけでなく、まだ見ぬ未来の世代の幸福までをも見据えた、長期的かつ普遍的な目標と言えるでしょう。
なぜ今、持続可能な社会が求められているのか?3つの背景
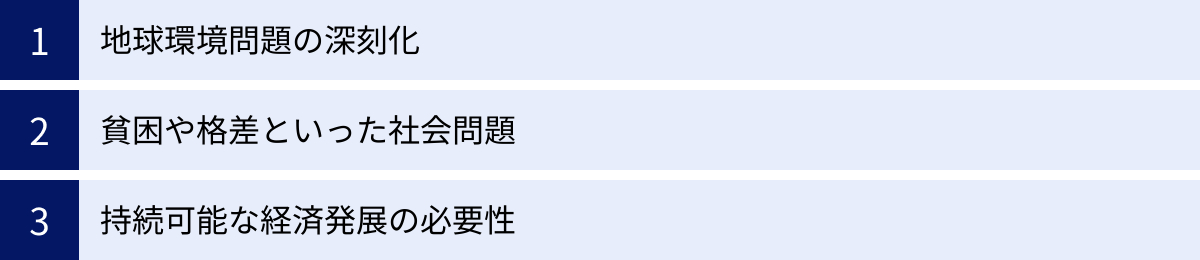
「持続可能な社会」という概念は、一朝一夕に生まれたものではありません。人類が地球上で活動を続ける中で顕在化してきた様々な課題が、私たちに従来のあり方を見直すことを迫っています。ここでは、なぜ今、これほどまでに持続可能な社会への転換が急務とされているのか、その主要な3つの背景を深掘りしていきます。
① 地球環境問題の深刻化
持続可能性が叫ばれる最も大きな理由の一つが、地球規模で進行する環境問題の深刻化です。私たちの生活や経済活動が、地球の許容量を超えるほどの負荷を与えているという事実が、科学的なデータによって次々と示されています。
地球温暖化
地球温暖化は、気候変動とも呼ばれ、人類が直面する最も喫緊の課題の一つです。産業革命以降、人間活動、特に化石燃料の燃焼によって大気中の二酸化炭素(CO2)をはじめとする温室効果ガスの濃度が急激に上昇しました。これにより、地球の平均気温が上昇し、気候システム全体のバランスが崩れ始めています。
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第6次評価報告書によると、2011年~2020年の世界平均気温は、産業革命前(1850年~1900年)と比べて約1.1℃上昇したとされています。わずか1.1℃の変化と侮ってはいけません。この気温上昇が、世界各地で観測されている猛暑、豪雨、干ばつといった異常気象の頻発・激甚化の主な原因であることは、もはや疑いの余地がないと科学的に結論付けられています。
(参照:気象庁 IPCC第6次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約 暫定訳)
このまま温暖化が進行すれば、海面の上昇による沿岸地域の水没、食料生産の不安定化、感染症の拡大など、私たちの生活基盤そのものを揺るがす、より深刻で不可逆的な影響が予測されています。地球温暖化の進行を食い止め、気候変動の壊滅的な影響を回避するためには、社会経済システム全体を脱炭素型へ移行させることが不可欠であり、これが持続可能な社会を求める強い動機となっています。
生物多様性の損失
私たちの暮らしは、食料、水、空気、医薬品の原料など、自然の生態系がもたらす様々な恵み(生態系サービス)の上に成り立っています。この恵みの源泉となるのが、多種多様な生き物とそのつながり、すなわち「生物多様性」です。しかし、このかけがえのない生物多様性が、今、かつてない速さで失われています。
生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム(IPBES)が2019年に公表した地球規模評価報告書は、人間の活動によって、地球上の推定800万種の動植物のうち、約100万種が絶滅の危機に瀕しているという衝撃的な事実を明らかにしました。その主な原因は、土地利用の変化(森林伐採や農地開発)、生物の直接的な搾取(乱獲など)、気候変動、汚染、外来種の侵入など、多岐にわたります。
(参照:環境省 生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム(IPBES)第7回総会結果について)
生物多様性の損失は、単に珍しい生き物がいなくなるという問題に留まりません。例えば、花粉を運ぶハチなどの昆虫が減少すれば、農作物の受粉が困難になり、食料生産に深刻な打撃を与えます。豊かな森林が失われれば、水源の涵養能力や土砂災害を防ぐ機能が低下します。生態系のバランスが崩れることは、巡り巡って私たち自身の生存を脅かすリスクであり、生物多様性を保全することは持続可能な社会の必須条件なのです。
資源の枯渇
現代の経済社会は、石油や石炭といった化石燃料、鉄や銅などの鉱物資源、そして水や森林といった再生可能な資源に至るまで、地球上の様々な資源を大量に消費することで成り立ってきました。しかし、地球は有限であり、その資源もまた無限ではありません。
特に、人口増加と経済成長に伴う消費の拡大は、資源の枯渇を現実的な問題として浮上させています。この問題を象徴するのが「アース・オーバーシュート・デー」という指標です。これは、人類による資源の消費量が、その年に地球が生み出すことのできる自然資源の量(生態系サービスの供給量)を超えてしまった日を指します。2023年のアース・オーバーシュート・デーは8月2日であり、これは私たちが1年分の資源をわずか7ヶ月ほどで使い果たし、残りの期間は未来の世代から資源を“前借り”している状態にあることを意味しています。
このまま大量生産・大量消費・大量廃棄の経済モデルを続ければ、資源価格の高騰や供給不安、さらには資源をめぐる国際的な紛争のリスクも高まります。有限な資源を効率的に、そして循環的に利用する社会経済システムへと転換し、将来の世代も資源の恩恵を受けられるようにすることが、持続可能性の観点から強く求められています。
② 貧困や格差といった社会問題
持続可能な社会が求められる背景には、環境問題と並んで深刻な社会問題の存在があります。グローバル化が進展し、世界全体の富は増大しましたが、その恩恵はすべての人々に平等に行き渡っているわけではありません。むしろ、国内外で貧富の差が拡大し、様々な格差が固定化・深刻化しています。
世界銀行の報告によれば、依然として世界では約7億人が1日2.15ドル未満で生活する「極度の貧困」状態にあります。こうした人々は、安全な水や食料、医療、教育といった基本的なサービスへのアクセスが困難であり、人間としての尊厳ある生活を送ることができません。
(参照:世界銀行「Poverty and Inequality Platform」)
また、開発途上国だけの問題ではなく、日本のような先進国内部でも格差は広がっています。所得や資産の格差、正規雇用と非正規雇用の格差、男女間の賃金格差(ジェンダーギャップ)、都市部と地方の地域間格差など、様々な形で不平等が存在します。
このような貧困や格差は、それ自体が重大な人権問題であると同時に、社会の不安定要因となります。機会の不平等は人々の意欲を削ぎ、社会全体の活力を失わせます。また、絶望や不満は社会的な対立や紛争の火種となりかねません。さらに、貧困状態にある人々は、短期的な生存のために環境を破壊するような行動(例:違法な森林伐採)を取らざるを得ない場合もあり、環境問題と社会問題は密接に連関しています。
すべての人々が機会を与えられ、その能力を最大限に発揮できる公正な社会を築くことなしに、社会全体の持続的な安定と発展はあり得ません。「誰一人取り残さない」という理念は、持続可能な社会を構築する上で、環境問題への取り組みと同等に重要な柱なのです。
③ 持続可能な経済発展の必要性
これまでの経済発展は、前述の通り、地球の資源を一方的に利用し、廃棄する「リニアエコノミー(線形経済)」を前提としていました。このモデルは、短期間で経済を大きく成長させ、私たちの生活を豊かにしてきた側面は否定できません。しかし、その裏で深刻な環境負荷と資源の浪費を生み出してきました。
地球環境の限界が明らかになり、社会的な格差が広がる中で、従来の経済成長モデルはもはや持続可能ではないという認識が世界的に共有されるようになりました。環境を破壊し、社会的なコストを外部に転嫁し続けるような経済活動は、長期的には立ち行かなくなります。
そこで注目されているのが、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の3つの要素を重視する「ESG経営」や、資源の循環を前提とする「サーキュラーエコノミー(循環型経済)」といった新しい考え方です。
企業が環境負荷の低減や人権への配慮といった社会的責任を果たすことは、もはや単なるコストや慈善活動ではありません。気候変動による物理的リスクや規制強化による移行リスクを回避し、環境配慮型製品を求める消費者の支持を得て、優秀な人材を惹きつけるなど、長期的な企業価値の向上と事業の持続可能性に直結する重要な経営戦略と見なされるようになっています。
経済活動を社会や環境から切り離して考えるのではなく、経済システムそのものを、環境の保全と社会の安定に貢献するものへと変革していく必要があります。これこそが、持続可能な社会の実現に不可欠な「持続可能な経済発展」の姿であり、現代社会が直面する大きな挑戦なのです。
持続可能な社会とSDGsの密接な関係
「持続可能な社会」という目標を語る上で、今や切り離すことのできないキーワードが「SDGs(エスディージーズ)」です。ニュースや企業のウェブサイトなどで頻繁に目にするこの言葉は、持続可能な社会の実現に向けた具体的な羅針盤としての役割を担っています。
SDGsは持続可能な社会を実現するための世界共通の目標
SDGsとは「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称です。これは、2015年9月に開催された国連サミットにおいて、加盟する193カ国全会一致で採択された国際目標です。2001年から2015年まで推進された「ミレニアム開発目標(MDGs)」の後継として、2016年から2030年までの15年間で達成を目指す「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の中核をなすものです。
SDGsの最大の特徴は、その普遍性にあります。MDGsが主に開発途上国の課題に焦点を当てていたのに対し、SDGsは先進国を含むすべての国が取り組むべき普遍的な目標として設定されています。そして、「誰一人取り残さない(leave no one behind)」という力強い誓いをその基本理念として掲げています。
具体的には、SDGsは持続可能な社会を築くための具体的な課題を網羅した、以下の17のゴール(目標)と、それらをさらに具体化した169のターゲット(達成基準)から構成されています。
| ゴール番号 | ゴール内容 | 関連する持続可能性の柱 |
|---|---|---|
| 1 | 貧困をなくそう | 社会、経済 |
| 2 | 飢餓をゼロに | 社会、環境 |
| 3 | すべての人に健康と福祉を | 社会 |
| 4 | 質の高い教育をみんなに | 社会、経済 |
| 5 | ジェンダー平等を実現しよう | 社会 |
| 6 | 安全な水とトイレを世界中に | 社会、環境 |
| 7 | エネルギーをみんなに そしてクリーンに | 環境、経済 |
| 8 | 働きがいも経済成長も | 経済、社会 |
| 9 | 産業と技術革新の基盤をつくろう | 経済、環境 |
| 10 | 人や国の不平等をなくそう | 社会 |
| 11 | 住み続けられるまちづくりを | 社会、環境、経済 |
| 12 | つくる責任 つかう責任 | 環境、経済 |
| 13 | 気候変動に具体的な対策を | 環境 |
| 14 | 海の豊かさを守ろう | 環境 |
| 15 | 陸の豊かさも守ろう | 環境 |
| 16 | 平和と公正をすべての人に | 社会 |
| 17 | パートナーシップで目標を達成しよう | (すべての柱を実現するための手段) |
この17のゴールを見てみると、前述した「持続可能な社会」を構成する3つの柱(環境・社会・経済)の要素がすべて網羅されていることが分かります。
- 社会の側面: ゴール1(貧困)、ゴール3(健康・福祉)、ゴール4(教育)、ゴール5(ジェンダー)、ゴール10(不平等)、ゴール16(平和・公正)などが直接的に対応しています。
- 環境の側面: ゴール7(クリーンエネルギー)、ゴール13(気候変動)、ゴール14(海洋資源)、ゴール15(陸上資源)などが中心的な役割を果たします。
- 経済の側面: ゴール8(働きがい・経済成長)、ゴール9(産業・技術革新)、ゴール12(持続可能な消費・生産)などが関連しています。
さらに、ゴール6(水・衛生)、ゴール11(都市)、ゴール12(消費・生産)のように、3つの側面が複合的に関わる目標も数多く設定されています。これは、持続可能な社会の実現には、環境・社会・経済の課題を個別に解決するのではなく、統合的に取り組む必要があるという考え方を明確に示しています。
そして、この統合的な取り組みを支えるのが、ゴール17の「パートナーシップで目標を達成しよう」です。SDGsの達成は、一国や一組織だけで成し遂げられるものではありません。政府、国際機関、企業、市民社会、そして私たち一人ひとりといった、あらゆるステークホルダーが協力し、それぞれの立場で役割を果たすことが不可欠であると強調されています。
要するに、SDGsとは、漠然としていた「持続可能な社会」という大きなビジョンを、世界中の誰もが共有し、具体的な行動を起こすための「世界共通の言語」であり、「具体的な行動計画」なのです。企業が自社の事業活動とSDGsのゴールを結びつけたり、自治体が地域の課題解決のためにSDGsを活用したり、そして私たちが日々の生活の中でSDGsを意識した選択をしたりすること。その一つひとつの行動が、相互に関連し合いながら、2030年のあるべき姿、すなわち持続可能な社会の実現へとつながっていくのです。
持続可能な社会を実現するための主な取り組み
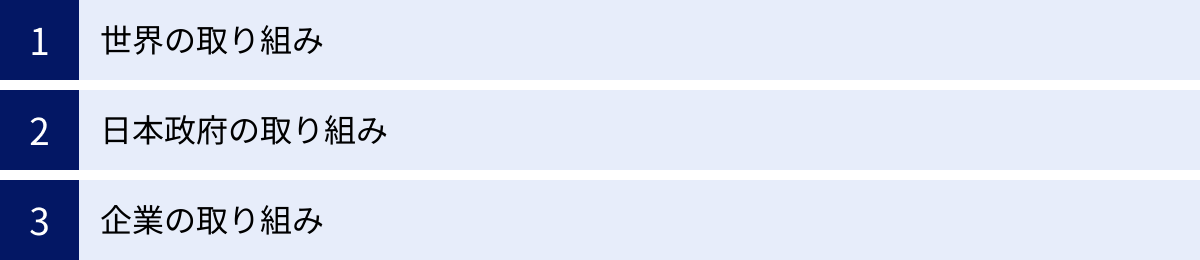
持続可能な社会の実現は、壮大な目標であり、特定の誰かだけの努力で達成できるものではありません。世界、国、企業、そして個人といった様々なレベルで、多角的な取り組みが連携して進められています。ここでは、それぞれの主体がどのような役割を担い、具体的な活動を展開しているのかを概観します。
世界の取り組み
地球規模の課題である気候変動や貧困などに対処するため、国際社会は協調して枠組みを作り、行動を進めています。
- パリ協定: 2015年に国連気候変動枠組条約締約国会議(COP21)で採択された、気候変動対策に関する歴史的な国際協定です。世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求することを世界共通の長期目標として掲げています。先進国・途上国を問わず、すべての参加国が温室効果ガスの削減目標(NDC:Nationally Determined Contribution)を策定・提出し、5年ごとに見直すことが義務付けられており、グローバルな脱炭素化を推進する上で中心的な役割を担っています。(参照:外務省ウェブサイト)
- 持続可能な開発のための2030アジェンダ: SDGsを中核に据えた、2030年までの国際社会全体の行動計画です。経済、社会、環境の3つの側面を統合的に扱い、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指します。国連は、ハイレベル政治フォーラム(HLPF)を毎年開催し、各国や国際機関によるSDGsの進捗状況をレビューし、さらなる行動を促しています。
- 各種国際機関による活動: 国連環境計画(UNEP)は環境分野の国際的な協力を主導し、国連開発計画(UNDP)は貧困削減や民主的ガバナンスの確立を支援しています。世界銀行や国際通貨基金(IMF)も、開発途上国への資金援助や技術協力などを通じて、持続可能な開発を後押ししています。これらの機関が専門的な知見や資金を提供し、各国の取り組みを支えています。
日本政府の取り組み
日本政府も、持続可能な社会の実現を国の重要な政策課題と位置づけ、様々な施策を推進しています。
- SDGs推進本部の設置: 2016年5月、内閣総理大臣を本部長、官房長官と外務大臣を副本部長とし、全閣僚を構成員とする「持続可能な開発目標(SDGs)推進本部」を設置しました。これにより、政府一体となってSDGsの達成に向けた取り組みを強力に推進する体制を整えました。(参照:首相官邸ウェブサイト)
- SDGs実施指針の策定: 日本がSDGs達成に向けて取り組むべき方向性を示した国家戦略です。2019年の改定版では、「ビジネスとイノベーション」「地方創生」「次世代・女性のエンパワーメント」を三本柱とし、以下の8つの優先課題を掲げています。
- あらゆる人々の活躍の推進
- 健康・長寿の達成
- 成長市場の創出、地域活性化、科学技術イノベーション
- 持続可能で強靱な国土と質の高いインフラの整備
- 省・再生可能エネルギー、気候変動対策、循環型社会
- 生物多様性、森林、海洋等の環境の保全
- 平和と安全・安心社会の実現
- SDGs実施推進の体制と手段
- 具体的な政策展開:
- グリーン成長戦略: 「2050年カーボンニュートラル」の実現に向け、エネルギー、輸送、製造業など14の重要分野で高い目標を設定し、予算、税、規制改革などあらゆる政策を総動員する産業政策です。
- 地域循環共生圏: 各地域が持つ豊かな自然資本(再生可能エネルギー、農林水産物など)を最大限活用し、地域内で資源と経済が循環する自立・分散型の社会を形成しようとする構想です。都市部への一極集中から脱し、持続可能な地域づくりを目指します。(参照:環境省)
- プラスチック資源循環戦略: 海洋プラスチックごみ問題や気候変動問題に対応するため、使い捨てプラスチックの排出抑制、リサイクルの徹底、再生材やバイオマスプラスチックへの代替などを進めるための包括的な戦略です。
企業の取り組み
現代において、企業は持続可能な社会を実現する上で極めて重要な役割を担っています。企業の行動は、環境、社会、経済に大きな影響を与えるため、その責任はますます重くなっています。
ESG投資の拡大
企業の持続可能性への取り組みを評価する上で重要な潮流となっているのが「ESG投資」です。これは、従来の財務情報だけでなく、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(企業統治)という非財務情報を考慮して投資先を選別する手法です。
- Environment(環境): CO2排出量削減への取り組み、再生可能エネルギーの利用率、水資源管理、廃棄物削減など。
- Social(社会): 従業員の労働環境、人権への配慮、サプライチェーンにおける児童労働・強制労働の排除、ダイバーシティ&インクルージョンの推進、地域社会への貢献など。
- Governance(企業統治): 取締役会の多様性、役員報酬の透明性、コンプライアンス遵守、汚職防止への取り組みなど。
かつては企業の社会的責任(CSR)はコストと見なされがちでしたが、現在ではESGへの配慮が長期的なリスクを低減し、新たな事業機会を創出することで、持続的な企業価値の向上につながるという認識が広がっています。年金基金や保険会社といった巨大な資金を運用する機関投資家がESG投資を積極的に推進していることも、この流れを加速させています。その結果、企業は投資家からの評価を得るためにも、ESG課題への取り組みを経営の根幹に据える必要に迫られています。
サプライチェーン全体での配慮
企業の責任は、自社の工場やオフィス内だけに留まりません。製品の原材料を調達し、製造し、顧客に届け、最終的に廃棄されるまでの一連の流れ、すなわち「サプライチェーン」全体における環境・社会への影響にも目が向けられています。
例えば、アパレル企業が安価なTシャツを販売している背景に、原材料である綿花の栽培における大量の農薬使用や、縫製工場での劣悪な労働環境(低賃金、長時間労働など)があった場合、その企業は消費者や投資家から厳しい批判を受け、ブランド価値を大きく損なう可能性があります。これは「レピュテーションリスク」と呼ばれます。
こうしたリスクを管理し、責任ある企業活動を行うために、多くの企業が以下のような取り組みを進めています。
- サプライヤー行動規範の策定: 取引先に対して、人権の尊重、労働安全衛生の確保、環境法令の遵守などを求める基準を設定し、その遵守を契約の条件とします。
- 監査(Audit)とモニタリング: 定期的に取引先の工場などを訪問し、行動規範が守られているかをチェックします。第三者機関による監査を導入する企業も増えています。
- トレーサビリティの確保: 製品に使用されている原材料が、「どこで」「誰が」「どのように」生産・調達されたのかを追跡できる仕組みを構築します。これにより、サプライチェーンの透明性を高め、問題の早期発見と解決につなげます。
自社だけでなく、サプライチェーン全体を巻き込んで持続可能性を高めていくことが、現代の企業に求められる重要な責務となっています。
持続可能な社会のために私たちにできること10選
持続可能な社会の実現は、国や企業だけの課題ではありません。私たち一人ひとりの日々の選択や行動が、社会全体を変える大きな力になります。ここでは、日常生活の中で比較的簡単に始められる、持続可能な社会に貢献するための具体的なアクションを10個、その理由や実践のヒントとともにご紹介します。
① 省エネ・節水を心がける
なぜ重要か?
私たちが家庭で使う電気やガス、水道は、その多くが限りある資源を使って作られています。日本の発電の多くは、依然としてCO2を排出する化石燃料に頼っています。また、安全な水を利用できるようにするためには、浄水や送水に多くのエネルギーが必要です。日々の省エネ・節水は、温室効果ガスの排出量を削減し、地球温暖化の防止に直接貢献します(SDGsゴール7, 13)。また、貴重な水資源を守ることにもつながります(SDGsゴール6)。
具体的なアクション
- 照明: 使っていない部屋の電気はこまめに消す。LED電球への交換は、消費電力が少なく長寿命なため、長期的に見て大きな省エネ効果があります。
- 空調: エアコンの設定温度を、夏は28℃、冬は20℃を目安に調整する。扇風機やサーキュレーターを併用して空気を循環させると、効率よく室温を調整できます。カーテンやブラインドを活用して、外からの熱の出入りを防ぐことも効果的です。
- 家電製品: 家電の主電源を切り、待機電力を削減する。省エネ性能の高い家電製品(「省エネ基準達成率」が表示されているもの)に買い替えることも有効な選択肢です。
- 節水: 歯磨き中や食器を洗っている間は水を出しっぱなしにしない。シャワーの時間を1分短くするだけでも、年間でかなりの節水になります。節水シャワーヘッドの利用もおすすめです。お風呂の残り湯は、洗濯や掃除、庭の水やりに再利用しましょう。
② ごみを減らし、正しく分別する
なぜ重要か?
ごみを大量に生産し続ける社会は持続可能ではありません。ごみを燃やせばCO2が発生し、埋め立てれば土地が不足し、土壌や地下水を汚染する可能性があります。ごみそのものを減らす(Reduce)、繰り返し使う(Reuse)、資源として再利用する(Recycle)という3Rを実践することは、資源の浪費を防ぎ、環境負荷を低減する基本です(SDGsゴール11, 12)。
具体的なアクション
- リデュース(減らす): 買い物の際は本当に必要かよく考える。過剰包装の商品は避け、簡易包装のものを優先的に選ぶ。マイボトルやエコバッグを持参し、使い捨て容器やレジ袋を断る。
- リユース(再利用): すぐに捨てずに、他の使い道がないか考える。着なくなった服はリメイクしたり、知人に譲ったり、フリーマーケットやリユースショップを活用する。修理して長く使える製品を選ぶことも大切です。
- リサイクル(再資源化): 自治体のルールに従って、プラスチック、ペットボトル、缶、びん、古紙などを正しく分別する。汚れた容器は軽くすすいでから出すなど、リサイクルの質を高める一手間を心がけましょう。
③ フードロスをなくす
なぜ重要か?
世界では飢餓に苦しむ人々がいる一方で、日本では年間約523万トン(令和3年度推計)もの食料が、まだ食べられるのに捨てられています。これは、国民一人ひとりが毎日お茶碗一杯分のご飯を捨てているのと同じ量です。食料を生産するには、土地、水、エネルギー、労働力など多くの資源が投入されており、フードロスはこれらの貴重な資源の無駄遣いであると同時に、廃棄・処理の過程で大量の温室効果ガスを発生させる原因にもなります(SDGsゴール2, 12)。
(参照:農林水産省ウェブサイト)
具体的なアクション
- 買い物の工夫: 買い物に行く前に冷蔵庫の中をチェックし、必要なものだけをリストアップする。ばら売りや量り売りを利用して、使い切れる分だけ購入する。すぐに使う食材は、スーパーの棚の手前にある販売期限が近い商品(てまえどり)を意識的に選ぶ。
- 保存と調理の工夫: 食材に合った方法で正しく保存し、長持ちさせる。野菜の皮や芯など、これまで捨てていた部分もレシピを工夫して活用する(ベジブロスなど)。
- 食べきる: 外食では食べきれる量を注文し、食べ残しをしない。家庭では作りすぎに注意し、残った料理はリメイクして翌日食べるなどの工夫をする。
- 期限表示の正しい理解: 「消費期限」は安全に食べられる期限、「賞味期限」はおいしく食べられる期限です。賞味期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではないことを理解し、自分の五感で判断することも大切です。
④ 環境に配慮された商品を選ぶ
なぜ重要か?
私たち消費者がどのような商品を選ぶかという「消費行動」は、企業に対する強力なメッセージとなります。多くの消費者が環境や社会に配慮した商品を求めるようになれば、企業もそのような製品の開発や生産に力を入れるようになります。私たちの「選ぶ」という行為が、市場を通じて持続可能な生産と消費のパターンを促進する力になるのです(SDGsゴール12)。
具体的なアクション
- 認証ラベルを参考にする: 商品を選ぶ際に、環境や社会への配慮を示す第三者認証ラベルを目印にしてみましょう。
- エコマーク: 生産から廃棄までの一生を通じて環境への負荷が少ないと認められた商品。
- FSC®(森林管理協議会)認証: 適切に管理された森林の木材を使用した紙製品や木製品。
- MSC「海のエコラベル」: 持続可能な漁業で獲られた水産物。
- レインフォレスト・アライアンス認証: 環境保全や農園労働者の生活向上など、厳しい基準を満たした農園で作られた製品(コーヒー、紅茶、バナナなど)。
- リサイクル素材や再生可能素材を選ぶ: 再生プラスチックやリサイクルコットンを使用した製品、植物由来のバイオマスプラスチック製品などを積極的に選ぶ。
- 長く使えるものを選ぶ: 安価ですぐに壊れてしまうものよりも、多少高くても丈夫で修理しながら長く使える、愛着の持てるものを選ぶ。
⑤ 地元の産品を消費する(地産地消)
なぜ重要か?
食料が生産地から消費者の食卓に届くまでの輸送にかかるエネルギーやCO2排出量を「フードマイレージ」と呼びます。遠い海外から輸入された食料は、フードマイレージが大きくなります。地元の産品(地産品)を購入することは、この輸送距離を短縮し、環境負荷を低減することにつながります。また、地元の農家や商店を応援し、地域経済の活性化にも貢献します(SDGsゴール8, 11, 12)。
具体的なアクション
- 地元の直売所やファーマーズマーケットを利用する: 新鮮で旬の農産物が手に入るだけでなく、生産者の顔が見える安心感もあります。
- スーパーでも産地をチェックする: 買い物をする際に、野菜や肉、魚などの産地表示を確認し、できるだけ地元や近隣の都道府県で生産されたものを選ぶ習慣をつけましょう。
- 地域の特産品に関心を持つ: 自分の住む地域にどのような特産品があるのかを知り、積極的に食生活に取り入れてみる。旅行先でもその土地ならではの食材を味わうのも良いでしょう。
⑥ フェアトレード商品を購入する
なぜ重要か?
私たちが日常的に消費するコーヒー、チョコレート、コットン製品などの中には、開発途上国の小規模生産者や労働者が、不利な取引条件や劣悪な労働環境のもとで生産しているものがあります。フェアトレードとは、こうした生産者に対して、公正な価格での取引を保証し、彼らの生活改善と自立を支援する仕組みです。フェアトレード商品を選ぶことは、貧困や児童労働といった問題の解決に貢献し、人や国の不平等をなくすための具体的なアクションです(SDGsゴール1, 8, 10, 12)。
具体的なアクション
- フェアトレード認証マークを探す: 国際フェアトレード認証ラベルなどが付いた商品が、スーパーや専門店、オンラインストアなどで販売されています。まずはコーヒー一杯、チョコレート一枚からでも、フェアトレード製品を試してみましょう。
- 背景を知る: なぜフェアトレードが必要なのか、その商品がどのような生産者によって作られているのか、背景にあるストーリーに関心を持つことが、より意味のある消費につながります。
⑦ マイボトルやエコバッグを持参する
なぜ重要か?
ペットボトルやレジ袋などの使い捨てプラスチックは、私たちの生活を便利にしましたが、その多くが適切に処理されずにごみとなり、深刻な海洋汚染を引き起こしています。海に流出したプラスチックごみは、海の生き物が誤って食べてしまったり、絡まって傷ついたりする原因となります。また、紫外線などで細かく砕けたマイクロプラスチックは、生態系への影響が懸念されています。マイボトルやエコバッグを持参する習慣は、使い捨てプラスチックの使用を直接的に減らし、豊かな海を守る行動です(SDGsゴール12, 14)。
具体的なアクション
- 習慣化する: 外出時には「スマホ、財布、鍵、マイボトル、エコバッグ」をセットで考えるなど、持ち歩くことを習慣にしましょう。職場や学校にマイボトルやマイカップを置いておくのも良い方法です。
- 様々なシーンで活用する: エコバッグはスーパーでの買い物だけでなく、コンビニやドラッグストア、書店など、あらゆる買い物シーンで活用できます。小さく折りたためるタイプを常にカバンに入れておくと便利です。
- 楽しむ: お気に入りのデザインのマイボトルやエコバッグを見つけると、持ち歩くのが楽しくなり、継続しやすくなります。
⑧ 公共交通機関や自転車を利用する
なぜ重要か?
自動車、特に自家用車は、移動に便利な反面、走行時にCO2や大気汚染物質を排出します。一人ひとりが移動手段を少し見直すだけで、社会全体の環境負荷を大きく減らすことができます。近距離の移動に自転車や徒歩を選んだり、通勤・通学に電車やバスといった公共交通機関を利用したりすることは、CO2排出量の削減に貢献し、大気汚染の改善や健康増進にもつながります(SDGsゴール3, 11, 13)。
具体的なアクション
- 移動手段を使い分ける: 天気の良い日や短い距離の移動は、意識的に自転車や徒歩を選ぶ。駅までバスで行き、そこから電車に乗る「パーク&ライド」ならぬ「サイクル&ライド」も有効です。
- 公共交通機関を積極的に利用する: 一度に多くの人を運べる公共交通機関は、一人当たりのエネルギー消費量やCO2排出量が自家用車よりも格段に少なくなります。
- 新しい移動サービスを試す: カーシェアリングやシェアサイクルといったサービスを利用すれば、車を所有しなくても必要な時だけ効率的に利用できます。
⑨ 寄付やボランティア活動に参加する
なぜ重要か?
環境問題や社会問題の解決には、専門的な知識や現地での継続的な活動が必要です。環境保護団体や人権支援団体、子ども食堂の運営団体などのNPO/NGOは、そうした専門的な活動を担う重要な存在です。時間やお金を寄付したり、ボランティアとして活動に参加したりすることは、こうした団体の活動を直接的に支え、社会課題の解決を加速させるパワフルな方法です(SDGsゴール1, 10, 15, 17など多岐にわたる)。
具体的なアクション
- 寄付: 自分が関心のあるテーマ(例:熱帯雨林の保全、途上国の女子教育支援など)で活動している信頼できる団体を探し、少額からでも寄付を始めてみましょう。月々の継続的な寄付は、団体の安定した活動基盤となります。ポイントや古本などで寄付できるプログラムもあります。
- ボランティア: 地域の清掃活動や植林活動、イベントの手伝いなど、気軽に参加できるボランティアもたくさんあります。自分のスキルや経験を活かせるプロボノ(専門性を活かしたボランティア)という形もあります。
⑩ 正しい情報を学び、周りに伝える
なぜ重要か?
持続可能な社会への変革は、社会全体の意識が変わらなければ実現しません。そのためには、まず私たち自身が、地球で何が起きているのか、どのような課題があるのかを正しく知ることが第一歩です。そして、学んだことを家族や友人、同僚と共有し、対話することで、関心の輪が広がり、社会全体で行動を起こす機運が高まっていきます。これは、質の高い教育(SDGsゴール4)であり、目標達成のためのパートナーシップ(SDGsゴール17)の基礎を築く行為です。
具体的なアクション
- 信頼できる情報源から学ぶ: 国連や政府機関、信頼できる研究機関やNPOのウェブサイト、関連書籍やドキュメンタリー映画など、様々な媒体から情報を得ましょう。
- 対話する: 学んだことや感じたことを、身近な人と話してみる。「フードロスを減らすためにこんな工夫を始めたんだ」「このコーヒーはフェアトレードなんだって」といった日常会話が、相手の気づきにつながることがあります。
- 発信する: SNSなどを通じて、自分が実践していることや、共感した取り組みについて発信するのも良い方法です。ポジティブな形で情報を共有することが、行動の輪を広げる鍵となります。
これらのアクションは、決して特別なことではありません。一つひとつは小さな一歩かもしれませんが、多くの人が実践することで、社会をより良い方向へ動かす大きなうねりとなります。まずは自分にできることから、楽しみながら始めてみることが大切です。